金融業界(銀行・証券・保険)の生成AIの活用方法・メリット・事例
投稿日:2025年2月19日 | 更新日:2025年7月31日

昨今、銀行・証券・保険といった金融業界では、インターネットバンキングの利用拡大や窓口の縮小により、ビジネスモデルの在り方が大きく変わってきています。また、人手不足やコスト削減に加え、業務を効率化しながら顧客満足度を向上させることが求められるようになりました。このような状況に対応するため、多くの企業でDXへの取り組みが進められており、AIやチャットボット、ボイスボットなどの導入が進んでいます。2023年以降は、さらなる業務効率化や顧客満足度向上へ期待が寄せられる「生成AI」に注目が集まり、導入を検討・実施する企業も増えています。
当記事では、金融業界で生成AIが注目されている理由をはじめ、生成AIを導入するメリットや活用方法から課題とリスク、金融業界における生成AIの導入事例まで詳しく解説します。
目次
生成AIとは?金融分野で注目される理由
生成AIの仕組みと概要
生成AI(Generative AI)は、大規模なデータセットを学習し、新しいテキスト・画像・音声・コードなど様々なコンテンツを生成するAI技術です。従来のルールベースや予測重視のAIとは異なり、生成AIは自然言語処理の分野で特に優れた性能を発揮します。
生成AIの代表例は、OpenAI社の「ChatGPT」やAnthropic社の「Claude」、Google社の「Gemini」などの大規模言語モデル(LLM)です。これまでのAIが「正解を分類する」ことに優れていたのに対し、生成AIは「自然な文章を生成する」ことで、金融業務における多様な非定型業務にも対応できる点が特徴です。
金融業界で生成AIが注目されている背景
金融業界では、業務の属人化や慢性的な人材不足が深刻化しており、限られた人員で多様な業務を遂行することが必要とされています。
また、非対面チャネルの拡大により、顧客接点のデジタルシフトが加速しており、リアルとデジタルの垣根を超えた柔軟な対応が求められています。さらに、マネーロンダリング対策や情報開示の透明性といったコンプライアンス対応も年々高度化しており、従来の人海戦術では限界を迎えつつあるのです。
このような多層的な課題に対して、生成AIは「人では処理しきれない情報の要約」「業務知識の自動整理」「個別最適化された顧客対応」といった形での貢献が期待されており、その導入に注目が集まっています。
金融業界で生成AIを導入するメリット・活用方法とは?
生成AIを金融業界で活用する主なメリットは以下です。
・業務の正確性とスピードを両立したレポート作成
・膨大な法令・ガイドラインの即時理解と要約
・コールセンター・営業現場での応対品質向上
・リスク評価・与信判断の定性情報の活用
・金融商品説明のパーソナライズ化と顧客接点の強化
それぞれ詳しく紹介します。
業務の正確性とスピードを両立したレポート作成
金融業界では、市況分析や投資レポート、融資稟議書など、正確性と速報性が求められる文書が日々作成されています。生成AIを活用することで、マーケットデータや定量情報をベースにしたレポートのドラフト作成が数秒〜数分で完了し、作成者はチェックと最終調整に集中できます。
これにより、従来は一日かかっていた作業が一時間以内に短縮されるケースもあり、レポートの品質と生産性を同時に高めることが可能です。また、属人化したノウハウの標準化などの効果も期待できます。
膨大な法令・ガイドラインの即時理解と要約
金融業界では、金融商品取引法、銀行法、FATF勧告※1など、大量かつ複雑な規制文書の理解が求められます。生成AIを社内ポータルやナレッジベースと連携させることで、規制文書や社内ルールを自然言語で要約・説明できる体制を構築可能です。
コンプライアンス部門や審査部門での属人的な暗黙知の可視化にもつながり、新人や非専門職でも一定の水準で対応できる環境が整います。
※1 FATF勧告:金融活動作業部会(FATF)が策定した、マネーロンダリングやテロ資金供与対策に関する国際的な基準
コールセンター・営業現場での応対品質向上
顧客との会話をリアルタイムで分析し、適切な対応フレーズや商品説明の補足を生成AIが提示する仕組みは、営業やコールセンター(コンタクトセンター)業務に革命的な変化をもたらすでしょう。
金融商品は複雑で説明責任も重いため、担当者ごとの知識差が顧客体験に大きく影響します。生成AIのサポートにより、経験や知識に依存しない均一な応対品質が実現できます。最新の規制や商品情報も正確に反映できるため、オペレーターの回答支援としても期待されています。
また、生成AIを活用し応対履歴を自動で書き起こし・要約し、オペレーター向けのFAQシステムやマニュアル等のドラフト作成や顧客管理システムとの連携などができる製品もあるため、ナレッジの蓄積や社内共有を図る取り組みに活用することも可能です。
リスク評価・与信判断の定性情報の活用
従来の与信審査は財務指標中心でしたが、生成AIにより、経営者インタビュー、IR資料、取引先レビューなどの定性データもスコアリングに活用可能になってきています。
これにより、財務情報だけでは見えにくい「経営者の信頼度」や「取引先の評判」といった、「数字にできないリスク」を補足的に評価することができるようになります。
金融商品説明のパーソナライズ化と顧客接点の強化
資産運用や保険商品などは、顧客のライフステージや価値観によって提案内容が大きく異なります。生成AIは顧客の属性をはじめ、過去の応対履歴やリスク許容度などをもとに、顧客ニーズに応じた商品説明を自然言語で生成できるため、画一的な提案ではなく、個別最適化されたコミュニケーションが可能です。
金融業界における生成AIの課題とリスクとは?
様々なメリット・活用方法がある生成AIですが、一方で気を付けなければいけない点もあります。金融業界における生成AIの主な課題とリスクは下記です。
・誤情報・ハルシネーションのリスク
・バイアスと公平性の確保
・説明責任の必要性
・情報漏洩とセキュリティ対策
誤情報・ハルシネーションのリスク
生成AIが出力する情報は一見もっともらしく思える一方で、事実と異なる情報を真実のように生成してしまう「ハルシネーション」と呼ばれる誤情報を含む場合があります。
特に金融業務では、利率、手数料、契約条件など数値や法的表現の正確性が強く求められるため、このような誤りが重大なトラブルに直結することも否めません。たとえば、ローン商品説明の誤記載や、税務上の処理に関する不正確なアドバイスは、顧客の不利益や法令違反に発展する恐れもあります。
そのため、自社の最新データやWebサイト・法令と連携させるなど、不正確・想定外の情報を返答しないよう制御する仕組みを設計することをはじめ、必ず「人間によるレビュー」を挟む体制が必要です。
バイアスと公平性の確保
生成AIは学習データに含まれる社会的・文化的なバイアス(先入観や偏り)をそのまま引き継ぐ傾向があります。金融業界においては、与信審査、保険料算定、住宅ローン審査などで生成AIを活用する場合、人種・年齢・性別・居住地などに基づく不当な差別や選別が生まれる場合があるため注意が必要です。
特に注意すべきは、生成AIが提示した説明文や審査根拠において、バイアスに基づく「差別的な表現」が紛れるケースです。これはESG(環境・社会・ガバナンス)経営やSDGsの観点からも見過ごせず、企業としての社会的信用を損なうリスクにもつながってしまいます。
公平性を担保するには、学習データのフィルタリングや評価指標の見直し、AI監査・倫理委員会の設置など、技術とガバナンスの両面での対策が求められます。
説明責任の必要性
金融サービスは「なぜこの提案なのか」「どういう根拠でこの判断に至ったのか」を顧客や監督当局に説明できることが前提です。生成AIの出力は、深層学習モデルのブラックボックス性により、出力の理由やロジックを人間が理解・説明しにくい構造になっています。たとえば、融資否決や保険加入の拒否といった判断の背景が不透明なままだと、顧客からの苦情や訴訟リスクにつながる恐れもあります。
この課題を回避するには、生成AIの出力に対して「人が意味を読み解ける」「根拠が参照可能」な形での可視化や、出力ログの記録・監査機能の実装が不可欠です。
情報漏洩とセキュリティ対策
生成AIを活用する際、ユーザーが入力する情報には顧客名、口座番号、資産状況、法人の機密データなどのセンシティブ情報が含まれるケースがあります。 これらの情報が、生成AIモデルへ学習されることで他の人の質問の回答に含まれてしまったり、生成AIサービス事業者のログに残る情報が外部からの攻撃によって漏れてしまったりするリスクがあるため、情報漏洩リスクや個人情報保護法違反の恐れが生じます。
送信前のマスキング処理、匿名化、アクセス制御といったセキュリティ措置が現実的な対策です。また、ChatGPTなど汎用LLMを従業員が勝手に使う「シャドーAI」問題も浮上しており、社内での利用ルール整備や教育の徹底が不可欠です。
生成AIでは、プロンプトと呼ばれる指示文を入力して使用しますが、プロンプトの入力内容を操作し、サービス提供者が抑止している情報を引き出そうとする攻撃手法もあります。AIが顧客になりすまして口座情報やクレジットカード番号を詐取するリスクも考えられるため、サイバーセキュリティへの対策が必要です。
金融業界における生成AIの導入事例
みずほ銀行:生成AIを活用した次世代コンタクトセンターシステムを提供
株式会社みずほ銀行(以下、みずほ銀行)では、2023年6月から社内向けテキスト生成AI「Wiz Chat」を導入し、2023年12月には「事務手続照会」と「与信稟議作成」の業務でもPoCを実施するなど、生成AIを活用した業務効率化を進めてきました。
2024年8月に、生成AIを活用した次世代コンタクトセンターシステムをリリースし、顧客サービスへの活用を進めています。次世代コンタクトセンターシステムは、「最先端のAI活用による顧客対応力の向上」と「チャネル統合とCRM連携によるシームレスなお客さま体験」を実現するものです。
具体的には、最先端の日本語生成AIを導入し、顧客との会話の分析やニーズの把握、迅速な回答と顧客に合った提案の支援や、FAQやチャットボットの回答精度を継続的に向上させることができます。
また、電話・チャット・LINEなど複数のチャネルからの相談内容をコンタクトセンター内で統合して引き継ぐことができるほか、コンタクトセンター内での応対内容を生成AIが自動でテキスト化・要約し、営業部や店舗とセキュアな環境で共有が可能となるそうです。
参照元:
株式会社みずほ銀行 プレスリリース
〈みずほ〉が見据える、10年後の金融。生成AIを活用して、業務効率化と新たなイノベーションの実現へ。
静岡銀行:営業活動の高度化・効率化をめざす「生成AIチャットボット」の開発に着手
株式会社静岡銀行(以下、静岡銀行)は、2024年10月より営業活動の高度化・効率化をめざし、新たな「生成AIチャットボット」の開発に着手しています。静岡銀行では、高度化・複雑化する顧客ニーズに的確かつ迅速に応えるため知識やスキルが求められ、経験の乏しい若手担当者などは事前準備に多くの時間を割くため生産性向上が課題となっていました。
過去の営業活動情報などを学習した「生成AIチャットボット」を通じて顧客の経営環境などの変化に柔軟に対応しながら最適な商品やサービスの提案につなげることで、業務の高度化・効率化を図るとのことです。
参照元:株式会社静岡銀行 プレスリリース
損保ジャパン:保険の情報照会に生成AIを導入、業務負担を軽減へ
損害保険ジャパン株式会社(以下、損保ジャパン)では、2024年10月より営業社員向けに生成AIを使った照会回答業務システム「おしそんLLM(仮称)」のトライアル運用を開始しました。損保ジャパンでは、代理店・営業店・本社間における保険の引受・規定に関わる照会内容の効率化と利便性の向上が課題となっていました。
課題解決のため、2017年には、散在するQ&Aなどを自然文で横断検索し、解決できない場合はそのまま検索できるナレッジ検索システムの使用を開始しました。課題解決力は向上した一方、コンテンツ作成とメンテナンスの負荷軽減も課題として挙がり、生成AIを活用した「おしそんLLM」の開発・トライアル運用に至りました。
「おしそんLLM」は、損保ジャパンが保有する膨大な規定が記載されたマニュアルやQ&Aデータなどを学習し、照会内容に最適な回答案を自動生成するシステムです。生成AIが作成した回答案と参照先文書をもとに、回答者が最終的な回答内容を作成できるため、回答者は一から文章を作成する作業が不要になり、照会対応における業務時間が削減されます。
損保ジャパンでは、トライアルを通じて社員からのフィードバックを収集し、システムの精度向上や機能拡充を図るとともに、業務効率化効果を検証し、将来的には、トライアルの結果を踏まえ全店への導入を検討するとのことです。
大和証券:AIオペレーターによる問い合わせサービス提供を開始
大和証券株式会社(以下、大和証券)は、2024年10月、生成AIを活用し、株価や市況ニュースなどのマーケット情報や、ログイン手続きやNISA関連などの一般的な内容に関する問い合わせに対応する「AIオペレーターサービス」の提供を開始しました。
新NISAの開始など、貯蓄から資産形成への大きな流れが生まれている中、今後さらなる投資家層の拡大に伴い、顧客からの問い合わせも大きく増えることが想定されます。こうした背景から、大和証券では生成AIをはじめとするデジタル技術を用いた金融サービスの提供により、顧客の利便性を向上し、顧客体験(CX)の変革を行うべく、「AIオペレーターサービス」の提供に至りました。
音声による会話形式の応答で、マーケット情報から事務手続きに関する内容まで広範に対応可能なAIオペレーターサービスの提供は、国内大手金融機関初の試みとのことです。
参照元:
大和証券株式会社 プレスリリース
山陰合同銀行:有人チャットの応対履歴を生成AIが自動で要約、ACWを軽減
株式会社山陰合同銀行は、DX戦略における「オムニチャネルプロジェクト」の一環として、2025年3月、モビルスが提供する有人チャット「MOBI AGENT(モビエージェント®)」、問い合わせ内容に応じて最適な問い合わせ先をWeb画面上で案内する「Visual IVR(ビジュアルIVR)」等の導入を決定しました。それに伴い、オペレーション支援AI「MooA®(ムーア)」を導入し、有人チャット対応後の応対履歴を生成AIが自動で要約し、カテゴリー分類を行うことで、オペレーターの平均後処理時間(ACW)※2を軽減します。
※2 ACW(After Call Work):利用者からの問い合わせ内容などを応対後にまとめ、専用システムへ記録入力する業務のこと
参照元:モビルス株式会社 プレスリリース
まとめ
生成AIの活用は、生産性の向上や業務効率化など企業へのメリットだけでなく、顧客の利便性向上など顧客満足度の向上にも寄与するため、多くの企業で検討・導入が行われています。銀行・損保・証券といった金融業界も例外ではなく、生成AIを活用した社内業務の効率化にはじまり、顧客対応でも活用されるなど、さまざまな事例が出てきました。生成AIは効果的に活用することで、金融業界が抱える課題の解決に役立つ一方、気を付けないといけない課題もあります。
当記事では、銀行や損保などの金融業界で生成AIが注目されている理由をはじめ、金融業界に生成AIを導入するメリットや活用方法から課題とリスク、金融業界における生成AIの導入事例について紹介しました。生成AIの導入を検討する際の参考にしていただけたら、幸いです。
当記事を執筆するモビルスでは、ナレッジベースの構築による回答サジェストやマニュアル検索を可能にするオペレーション支援AI「MooA」をはじめ、コールセンター(コンタクトセンター)の顧客体験(CX)向上を通じて企業の競争力を高め、収益を最大化するための総合的な支援を提供しております。
AIボイスボットやAIチャットボット、自己解決を促すビジュアルIVRなど、顧客満足度につながる幅広いニーズに対応できるソリューションを開発提供しています。ぜひご相談ください。
オペレーション支援AI「MooA」紹介資料
MooA®(ムーア)は生成AIや独自のAI技術を取り入れた、オペレーターの応対業務の負担を軽減し、応対業務全体の短縮化とVOCの活用を促進するオペレーション支援AIです。チャットボットやボイスボットと連携しながら、応対中のオペレーターの回答業務を支援します。機能、解決できることなどを紹介資料にて掲載しています。
下記より、ダウンロードいただけます。ぜひご覧ください。
https://go.mobilus.co.jp/l/843543/2024-04-30/by8ypg
銀行業界向けCXソリューション紹介資料
導入事例をはじめ、銀行業界向けのCXソリューションを紹介する資料です。下記よりダウンロードいただけます。ぜひご覧ください。
https://go.mobilus.co.jp/l/843543/2025-07-14/c7bvmc
保険業界向けCXソリューション紹介資料
保険業界のコンタクトセンター が抱える課題と、その解決策として注目される自動対応の取り組みについてご紹介します。よくある問い合わせの自動化による業務負荷の軽減や、問い合わせ窓口の対応範囲を拡大する業務フローを解説するとともに、生成AIの活用や実際の導入事例を交えながら、業務効率化と顧客体験 (CX)の向上を両立する最新の動向をお届けします。

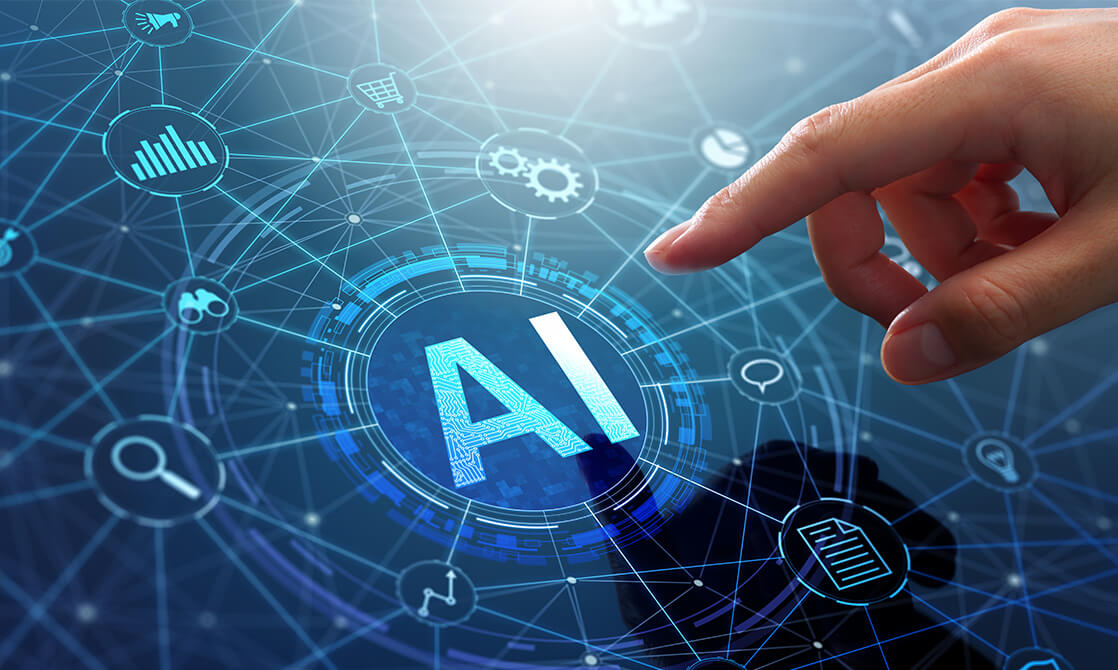













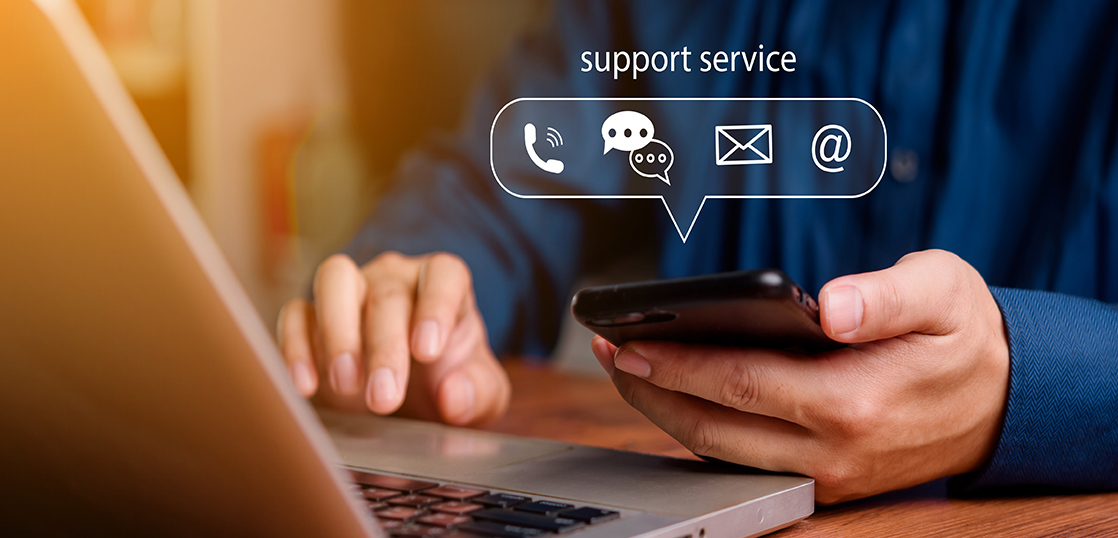


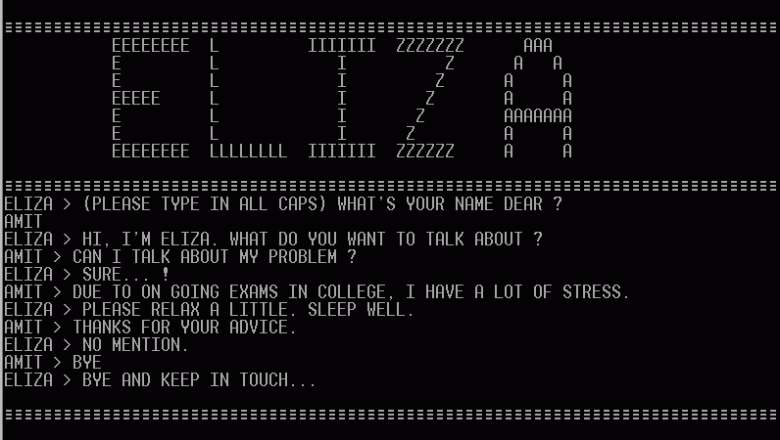
_web.jpg)


