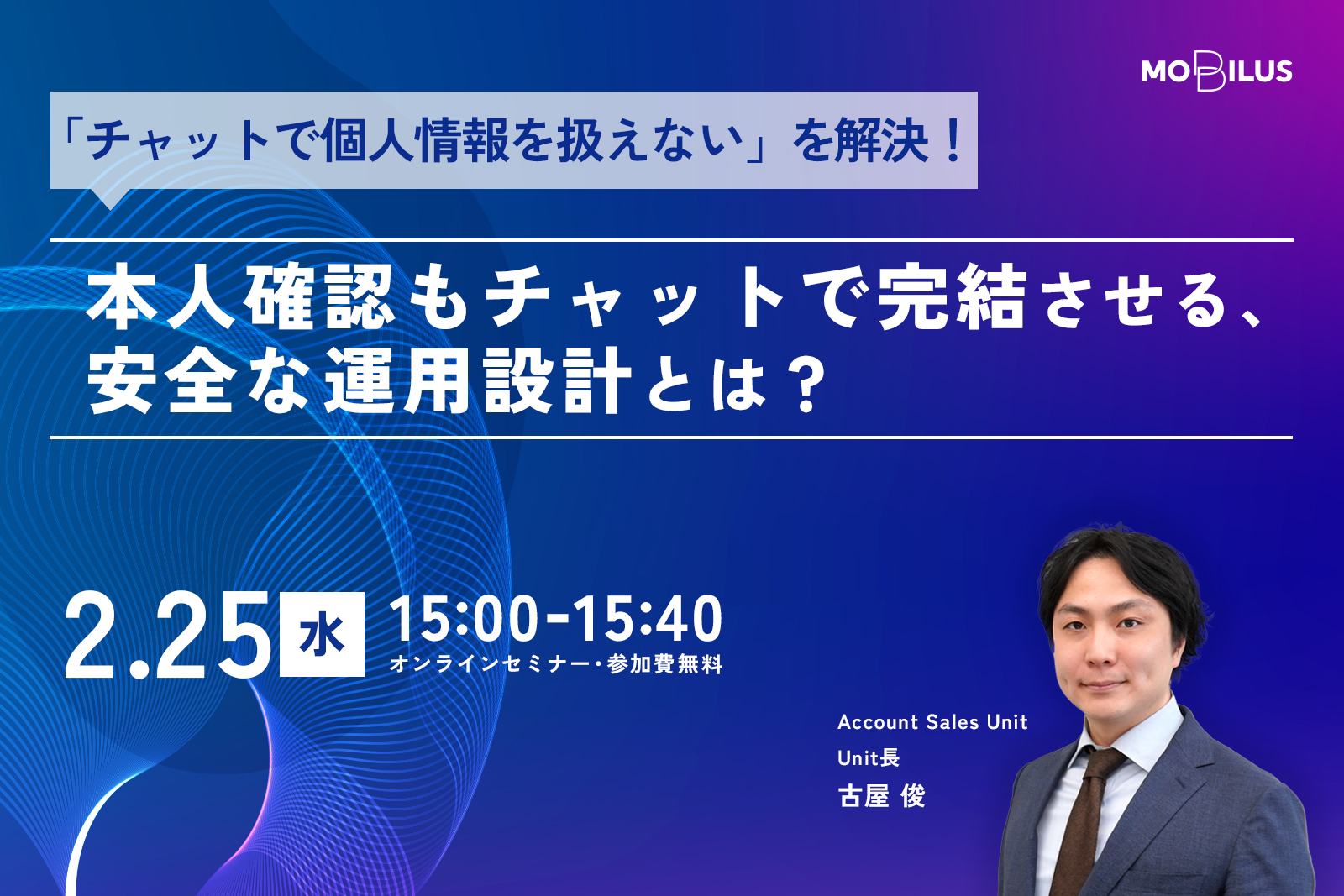コールセンター(コンタクトセンター)におけるCPHとは?計算方法と改善の秘訣6選
投稿日:2025年3月31日 | 更新日:2025年3月30日

コールセンター(コンタクトセンター)運営において、生産性向上を課題として挙げている企業は多いのではないでしょうか。生産性を管理する上で、KPIや指標の適切な設定・把握は欠かせません。複数ある重要なKPIの中で、今回は「オペレーター1人あたりが1時間に処理できるコール件数を表す指標」である「CPH」について紹介します。
当記事では、コールセンターにおけるCPHの基礎知識から、コールセンターのKPIとしてCPHを用いる際の注意点やCPH向上のための施策まで詳しく解説しますので、ぜひご覧ください。
目次
コールセンターにおけるCPH(Calls Per Hour)とは?
CPHの意味
CPH(Calls Per Hour)とは、コールセンターにおいてオペレーター一人あたりが1時間に処理できるコール件数を表す指標です。
「1時間あたりのコール対応件数」や「1時間あたりの通話数」と表現されることもあり、コールセンターの生産性や効率性を測る上で非常に重要です。特に、インバウンド(受電)型のコールセンターでは、どれだけ効率よく多くの顧客からの問い合わせを処理できるかが、顧客満足度や待ち時間に直結するため、CPHは重要な指標となっています。
一方、アウトバウンド(発信)業務でも、リストに基づくアプローチをどれだけ効率的に行えるかが売上や成約率に影響を与えるため、CPHの概念は外せません。
CPHの計算方法
CPHの基本的な計算式は下記の通りです。
CPH = (対応したコール数) ÷ (稼働時間 【時間】)
例えば、あるオペレーターが8時間勤務の中で、実際にコール対応に費やした稼働時間が7時間だったとします。そこで1日に対応したコール数が100件だとすると、
CPH = 100件 ÷ 7時間 = 14.28
この場合、1時間あたり約14件のコールに対応していることになります。
ただし、オペレーターの休憩時間や研修・ミーティングなどで実際にコール対応に充てられない時間も生じています。正確な稼働時間をどのように定義するかは企業ごとに異なるため、指標として比較する場合は、同一の条件下で計算することが重要です。
コールセンターのKPIとしてCPHを用いる際の注意点とは?
「CPHは高ければ良い」という思い込みを捨てる
CPHの向上は、コールセンター運営における生産性の上昇を意味します。同じ人数でより多くの問い合わせに対応できれば、コールセンターの運営コスト削減につながるだけでなく、顧客からの着信を取りこぼすリスクの低減にも寄与するためです。
また、CPHが高まることで、待ち時間の短縮や問い合わせへの迅速な回答が期待できます。適切な品質が担保された上でのスピーディな対応は、顧客満足度(CSAT)やブランドイメージ向上にも好影響を与えます。
ただし、「早く対応しよう」と急ぎすぎるあまり、顧客と十分なコミュニケーションがとれず、問題解決が不十分なままやり取りが終わってしまうという懸念も無視できません。また、オペレーターの精神的ストレスが増大することにもつながる恐れがあります。「CPHは高ければ良い」と、CPHの向上のみを評価とするのではなく、生産性と品質、オペレーターの健康やモチベーションのバランスをいかに保つかを考えることが欠かせません。
部門ごと・オペレーターごとに目標値を設ける
コールセンター内でも、製品サポート部門、クレーム対応部門、営業アウトバウンド部門など、対応する問い合わせの性質が異なる場合があります。CPHを評価する際には、業務内容ごとに目標値を設定し、比較検討することが重要です。
一律の基準で「CPHが高い・低い」と判断すると、業務特性を無視した不公平な評価が生まれ、オペレーターのモチベーション低下に繋がる恐れがあります。

CPHを向上させるための施策・ポイントとは?
コールセンターのKPIとしてCPHを用いる際の注意点を踏まえた上で、CPHを向上させる方法を考えていきます。主な施策・ポイントは以下の6つです。
①トークスクリプトの整備
②マニュアルの拡充
③オペレーターの研修・育成
④業務プロセスの見直し
⑤システムの最適化
⑥マルチチャネルの活用
それぞれ詳しく紹介します。
①トークスクリプトの整備
トークスクリプトを整備することで、オペレーターが顧客対応の際に迷うことなくスムーズに受け答えを行えるようになり、通話時間の短縮や応対品質の安定化が期待できます。
具体的には、よくある質問やクレーム対応などを想定した文言をあらかじめ準備し、誰が対応しても一定以上のクオリティを保てるようにします。顧客の心理を踏まえたフロー構成にしておくと、やり取りが円滑に進む点もポイントです。
ただし、スクリプトに寄りかかりすぎると機械的な応対になりがちなため、オペレーターが臨機応変にアドリブを加えられる余地を残しておくと良いでしょう。また、作ったら終わりではなく、実際の通話ログを振り返りながら定期的に改善・更新していくことが大切です。
②マニュアルの拡充
マニュアルの充実度が高いコールセンターほど、オペレーターは必要な情報を素早く参照し、正確かつ効率的に対応を進めやすくなります。業務フローや操作手順だけでなく、トラブルシューティングやエスカレーションポリシーなど実務で頻出する内容を網羅しておくと、迷いやミスを減らすことが可能です。
紙媒体ではなく、オンライン上で最新版のマニュアルを共有できる仕組みを作れば、更新が容易な上にスタッフ全員が同時に閲覧可能となるため、マニュアルの活用度が一段と高まります。また、マニュアルに沿った対応で問題が起きた場合には内容を見直し、現場のフィードバックを活かして随時ブラッシュアップしていくことが大切です。
③オペレーターの研修・教育
コールセンター業務で最も重要なリソースが「人」である以上、オペレーターのスキルアップはCPH向上のカギを握っていると言えます。
基礎研修では商品やサービスの知識を深め、顧客ニーズを把握した上でのコミュニケーション術を学びます。ロールプレイングや先輩オペレーターのモニタリングなどを通じて、実際の電話応対時に役立つ実践力を身につけていきます。
次にシステム操作の習熟度を高めることも重要です。複数のツールをスムーズに切り替えながら情報を入力・検索できれば、1件あたりの対応時間を短縮できます。
また、研修や評価制度を整えることでモチベーションを高め、離職率を下げる施策も合わせて行うと、職場全体のパフォーマンス向上にも効果的です。
④業務プロセスの見直し
優秀なオペレーターが揃っていても、業務プロセス自体に無駄があればCPHは上がりにくいものです。顧客が電話をかけてから用件を完了するまでのフローを明確化し、重複作業や煩雑な承認手続きをできる限り削減していくといった見直しが必要です。
特に、他部署へのエスカレーションが必要なケースでは、権限や連携ルールを明確に定めることで、対応が長引くことを防ぐことができます。プロセスを見直す際には、現場の声を積極的に取り入れ、PDCAサイクルを回しながら常に最適化を目指すことが重要です。
⑤システムの最適化
オペレーターが複数のシステムを操作する際に無駄な画面遷移が多いと、1件あたりの対応時間が長引きCPHが下がってしまいます。CRM(顧客管理)ツールなどを活用し、一つの画面で必要情報を確認・入力できるようにすることで操作負荷を軽減することが可能となるほか、IVR(自動音声応答)やボイスボット(AI電話自動応答システム)、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入すれば、定型的な問い合わせやデータ入力を自動化でき、オペレーターが付加価値の高い業務に集中できるようになります。
さらに最近では生成AIを活用し、応対履歴の書き起こしや要約の自動化、FAQの下書き生成の自動化も可能になるなど、オペレーターの業務負荷を軽減できるシステムの幅が広がっています。
⑥マルチチャネルの活用
問い合わせチャネルを電話だけに限定していると、コール量の多い時間帯にオペレーターが不足し、待ち時間が長くなりやすいという課題が生じます。
チャットやメール、SNSなど複数のチャネルを用意し、自己解決が可能な問い合わせにはチャットボットやFAQを案内する仕組みを整えることで、電話に集中する問い合わせ数を減らすことができます。また、事前ヒアリングや定型的な手続きなどボイスボットやチャットボットで対応できる範囲は自動化し、人の対応が必要な場面でオペレーターに引き継ぐことで、オペレーターの応対時間を減らすことも可能です。このようなマルチチャネルの活用は、結果的にCPHの向上につながります。
なお、マルチチャネル対応を進める際は、問い合わせ履歴を一元管理できるようにして重複対応を防ぐなど、運用面の整備も欠かせません。
まとめ
「CPH」は、コールセンターの生産性を管理する上で重要な指標の一つです。CPHの向上はコールセンターの生産性向上において欠かせないものである一方で、単に早く対応することを主軸においてしまうと顧客とのコミュニケーションが不十分になったり、オペレーターの精神的負荷が上がったりなど注意すべき点も存在します。こうした注意点を踏まえた上で、トークスクリプトの整備やマニュアルの拡充、オペレーターの研修・育成、業務プロセスの見直し、システムの最適化やマルチチャネルの活用といったCPHを向上するための施策を打っていくことが重要です。
当記事を執筆するモビルスでは、顧客体験(CX)ナレッジベースの構築による回答サジェストやマニュアル検索を可能にするオペレーション支援AI「MooA」をはじめ、コールセンター(コンタクトセンター)のCX向上を通じて企業の競争力を高め、収益を最大化するための総合的な支援を提供しております。
AIボイスボットやAIチャットボット、自己解決を促すビジュアルIVRなど、顧客満足度につながる幅広いニーズに対応できるソリューションを開発提供しています。ぜひご相談ください。
オペレーション支援AI「MooA」紹介資料
MooA®(ムーア)は生成AIや独自のAI技術を取り入れた、オペレーターの応対業務の負担を軽減し、応対業務全体の短縮化とVOCの活用を促進するオペレーション支援AIです。チャットボットやボイスボットと連携しながら、応対中のオペレーターの回答業務を支援します。機能、解決できることなどを紹介資料にて掲載しています。
下記より、ダウンロードいただけます。ぜひご覧ください。
顧客体験を最大化するCX戦略支援 CX Consulting
モビルスでは、クライアントの顧客体験を最大化するため、カスタマージャーニーマップ作成や定量的調査を通じたCX戦略立案・策定を支援しています。解決するお悩みや、CXコンサルティングの流れ等の詳細は、以下からご覧ください。

 モビルス株式会社
モビルス株式会社
CX向上に導くモビルスのカスタマーサクセスメニュー
モビルスでは、プロアクティブなサポートで企業を成功に導くため、CXを向上させる伴走型のサポート体制(カスタマーサクセスメニュー)を整えており、導入前から導入後までの全フェーズを支援するサービス提供をしています。
下記の記事で詳しく紹介しております。ぜひご覧ください。










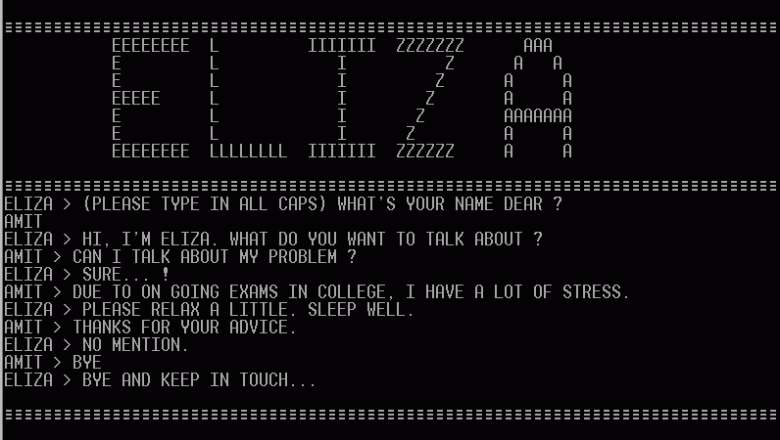


_web.jpg)