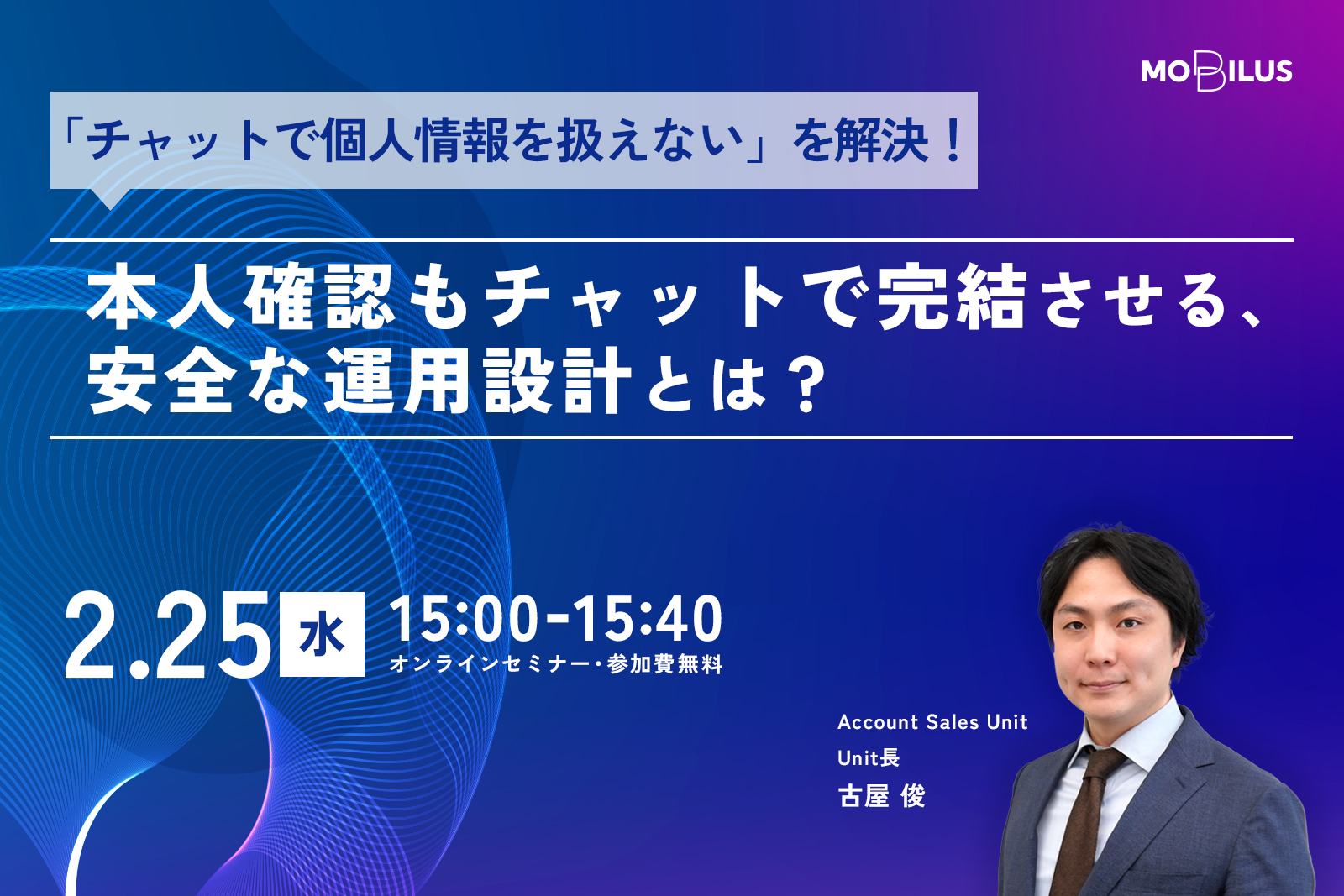海外と日本のIT経営者の経営思想と、生成AIで激変する数年先への投資とは。世界的CE企業のベリントシステムズとモビルスが対談【前編】
投稿日:2024年5月16日 | 更新日:2025年4月28日

「生成AI」の登場は、CX(Customer Experience)やCE(Customer Engagement)の向上にも期待が寄せられています。生成AIの活用を模索する企業も多い中、激変する数年後へ向けたITの投資をどのように考えていくべきでしょうか。
米国に本社を置き、CX・CEの取り組みで世界最先端の “CXオートメーション・カンパニー”として世界各地で企業と顧客の関係性構築を支援しているVerint Systems Inc.。その日本法人のベリントシステムズジャパン株式会社(以下、ベリント)代表取締役社長 古賀 剛 氏と、コンタクトセンター向けCXソリューションを開発・提供するモビルス株式会社 代表取締役社長 石井 智宏との対談が実現。
海外と日本の「生成AI」トレンドや取り組みの違いや、DXやCXに対する海外と日本企業の経営者のIT投資傾向や考え方の違いが生むもの、数年先の日本市場でのIT投資の展望などについてお話いただきました。前編・後編の2回にわたってお届けします。今回は前編をお届けします。後編はこちら。
【前編】
【後編】
■対談メンバー
ベリントシステムズジャパン株式会社 代表取締役/ベリントシステムズアジア太平洋地域 日本担当副社長 古賀 剛 氏
2004年からベリントジャパンのセールスディレクターとして多くの顧客を獲得し、現在のベリントの営業基盤を形成。2018年1月にベリントシステムズジャパンの代表取締役に就任、ベリントシステムズAPACの副社長を兼任。高いシェアを誇る通話録音のみならず、ベリントの多岐に渡るコンタクトセンター向けアプリケーションや、事務業務部門の業務可視化・最適化を図るバックオフィス向けソリューション、また近年ではオープンプラットフォームとAIボットによるCX自動化ソリューションを日本市場に展開している。
モビルス株式会社 代表取締役社長 石井 智宏
1998年 早稲田大学卒、2009年 ペンシルバニア大学ウォートンMBA取得。ソニー株式会社にて11年間ラテンアメリカ市場におけるセールスマーケティングに従事。MBA取得後、国内投資ファンドにて執行役員。その後ソニー会長率いるクオンタムリープ株式会社のエグゼクティブパートナーとして多数の日本企業の海外進出を実行支援。2014年モビルスに参画。受託開発中心のビジネスから業態チェンジをし、主力製品「MOBI AGENT」や「MOBI BOT」「MOBI VOICE」などをリリース。企業のコンタクトセンターや自治体向けに製品の提供、導入支援を行っている。
海外ではスピードや規模感が桁違い。生成AIは日本企業でも導入への敷居が低い
ー海外と日本の「生成AI」トレンドや、取り組みの違いについてお聞かせください。
古賀氏:
先日、タイで開催されたコンタクトセンターのイベントに出展してきましたが、木曜日の閉幕後、翌週水曜日にはトルコの企業から製品の発注が届きました。日本企業では製品導入前にPOC(Proof Of Concept:概念実証)を行うことが多く導入までに時間がかかりますが、海外の企業は「時間がもったいない」という考え方で、スピード感が全く違います。
「GBS(グローバルビジネスセンター)」という発想が、インドやベトナム、フィリピンでは盛んです。巨大な企業のバックオフィスを一ヵ所に集め、新規受付や解約申し込みなどに対応しています。十数万から数十万席の規模になるため、得られる効率化の効果が桁違いです。

録音音声認識は当たり前、応対品質評価を自動化するといった差別化をしないとGBSのビジネスでは勝てない世界で、スピード感や規模感が日本と全く違っていました。
日本企業では、勉強や検証に時間をかけるため導入までのスピードが遅く、もったいないと感じています。とは言え、生成AIに関してはこれまでと違い、お客さまが自分たちで試せる点は大きく、導入に対して敷居が低くなったのではないでしょうか。相当革新的なことです。
一方、法整備の問題や開発者の悪意や宗教差別などをいかに考えるかという課題もあります。我々はメーカーとしてどうしていくのか、今年最も問われることだと考えています。
石井:
「GBS」というトレンドは知りませんでした。スピード感や規模感が日本と相当違っていますね。
ーベリントシステムズが考える生成AIの活用や、展開するサービスについて教えてください。
古賀氏:
生成AIは大変お金がかかるので、すべてにAIを介すと甚大なコストがかかってしまいます。核になるのはやはりアプリケーションです。アプリケーションがあって、生成AIと組み合わせていく、我々のプロフェッショナル領域に対して生成AIを使っていく、という立場で製品開発を行っています。
生成AIは使うのですが支配されないことが重要です。弊社には、呼量予測やシフト交換などワークフォースマネジメント(以下、WFM)や、応対品質に関するさまざまなアプリケーションがあります。これらに関するAIを提供していこうとしています。

WFMの呼量予測に関して述べると、我々には20年間予測してきた統計データやアライアンスがあるので、それに対する誤差や季節変動などの差分のみを生成AIに聞く方が、コスト的にも時間的にも有益ではないでしょうか。
コンプライアンスについても同じです。全通話を生成AIにチェックさせると大変な金額になります。弊社では証券会社のお客さま向けに、これまでたくさんのコンプライアンスチェックのための音声認識を行ってきました。全体の通話から0.1%まで絞り、疑わしい通話だけをリスクチェックできるアプリケーションがあります。
基本的なアプリケーションをしっかり使い、その差分をAIに任せる。生成AIの良いところを適切な規模で使いましょうという考え方です。生成AIも一社だけでなく、いろんな会社と契約し、自社の生成AIも併用して、多様に選べるようにしています。
一時のブームで終わらぬよう適切な使い方を。効果は確実に出る
ーDXやCX、生成AIの活用についても日本は遅れているように感じます。脱却するためにどうしていくのが良いでしょうか?
古賀氏:
日本企業のみなさんもいろいろ試されているようですが、コストに見合わないという課題を抱えています。ただ、やらないといけないという機運は高まっています。「ChatGPT(生成AI)を使うように」とトップダウンで話は来るので、使わないといけないという認識でプロジェクトを組むものの、どう使ったら良いか分からない、というのが今の日本社会で起きている現実です。
ここ1、2年、ChatGPTへの動きが加速していますが、費用対効果が出ないと興味を引けない恐れがあります。そこを心配しています。「一緒に使い方を考えましょう」と伝えたいです。
音声認識も一時期急激に盛り上がって、その後沈静化した時代がありました。しかし、今は音声認識を活用することが当たり前になってきました。
ですので、生成AIも同じだと思います。この1、2年一気に盛り上がり、一度落ち着き、そこから本当の安定期に入り正しい使い方ができると思っています。ただ、そのスピードは早いですよね。
石井:
ChatGPTの環境をご自身で試せることは、広がりを後押ししています。一方で、社内の取り組みとして成功した話は、ほぼ聞いたことがありません。そもそも使いこなせていないという問題があります。気軽に試せるChatGPTはコストやキャパシティも低いので、全オペレーションには使えません。
古賀氏:
それを変える施策はありませんか?
石井:
適切に使用した場合の効果は、確実に出るということは実感しています。チャットボットの黎明期も同じですが、何がしたいか要望を聞き、受託開発ではないですが専用のシステムを作ってしまうという事業が当分伸びると考えています。まずはそこを手がけています。

効果を出しやすいところはオペレーター支援やバックエンドの業務支援として、アフターコールワークや、後処理の自動化です。生成AIを使ったオペレーション支援は、ナレッジの整備が不可欠ですが、ナレッジを整備して持っている企業はほぼなく、ナレッジを作ることが当面の事業になっていくでしょう。
古賀氏:
素晴らしいです。
当社はイギリスの大きなナレッジカンパニーを買収し、エンタープライズ向けの「ナレッジマネジメント(KM)」と、手軽にナレッジを組み立てる「KMプロ」の2種類の製品を販売しています。
なぜ我々がナレッジを重視するかというと、「single point of truth」と言いまして、真理は一ヵ所にあるべきで分散してはいけないという考えです。チャットボットもオペレーターもWebも、同じ答えでないといけません。
例えば「料金改定します」というときに、修正しなければいけない場所が30ヵ所もある、というお客さんばかりです。こうした状況は日本だけです。海外では、ナレッジ化の取り組みは5年前、10年前には完了しています。
これがまさにDXです。DXは知を集中させる、知をデジタル化し俗人化させないことにつきます。まず、知識を一ヵ所に集約し、すべてのアプリケーションからアクセスできるようにすることです。
石井:
ナレッジの整備は多くの会社にとって重大な課題です。同じ製品のマニュアル一つとってもカテゴリーが統一されていない。マニュアルの作成年代によって構成がバラバラ、タグ付けも一切されていない、マニュアルのファイル名のどこにもモデル名が記載されていない、ということがよくあります。日本企業の多くは、生成AIに使えるナレッジのルールが全くできていないのです。
Webサイトはマーケティング部門の担当なのでサポート部門は触れない、ということも多々あります。ここで多くの会社は行き詰まってしまうのです。

古賀氏:
まさに情報のサイロ化ですね。Webに関する情報はマーケティング部門が、製品に関する情報は開発部門が持っているといった中で、情報共有するときにも、ナレッジマネジメントがしっかりされていることが大切です。
コロナ禍でも感じたことですが、混乱している最中は情報が錯綜します。知識を統一・統制でき、コミュニティ内で話し合って、外に出して良い情報かどうか管理する必要があります。知識を体系立って持ち、社内外含め適切に情報を出していく、もしくは出さない。ナレッジマネジメントができるかどうかは、企業にとって生命線だと思います。だからこそ、日本企業が取り組むべきところなのです。
Webの行動履歴からVOCまでカスタマージャーに活かす
石井:
カスタマージャーニーオーケストレーション※は、重要なテーマです。コンタクトセンターに寄せられたお客さまの声(VOC)を他部門に提供し、カスタマージャーニーに活用していくと言う話が実際に出始めています。
弊社も「The SupportTech Company」として、課題の多いサポートという領域において、技術で革新していくと言い続けてきました。しかし、事業範囲がサポートに留まらなくなってきているため、「CX-BrandingTech.」にリブランディングする予定です。

これまでは、企業のブランディングの根幹は広告宣伝が中心でしたが、今後はCXが企業のブランディングの根幹になると考えています。我々は、CXを支えるテクノロジーを開発していく会社ですと路線を変更していきます。
カスタマージャーニーオーケストレーションの考え方は非常に重要ですが、日本企業に浸透する難しさも感じています。
古賀氏:
当社は元々記録屋なので、ボットで話しているところを全部記録し音声も録音し、Webの行動履歴も記録し、調査・分析もさせていただくというのが本来の姿です。顧客体験のジャーニーや従業員の満足度も記録させていただくと、そこで初めてCXを包括的に分析できるので、最初から最後まで一貫して担っています。
最近は生成AIという言葉を使わず、カスタマーエクスペリエンス(CX)もしくはカスタマーエンゲージメント(CE)AIと言っています。なんでもできるAIではなく特化したAIを開発していくことが我々の使命だと考えています。
石井:
確かにAIは全知全能である必要はないですよね。
今までは顧客の声や応対履歴が一番情報量の多いところでしたが、それ以前のWebの行動履歴といった情報も使っていくようになると思いますが、このあたりについて、どうお考えですか?
古賀氏:
弊社のソリューションは、Webサイトでどこを何秒触っていたかを記録することができ、分析結果としてヒートマップが出てきます。
あるお客さまの例では、スマホで最初の画面に表示されるページはクリック率が85%ほどでした。2スクロール目だと60%、一番下は30%以下です。せっかくキャンペーンをやっていても、バナーが一番下にあると誰にも読まれません。その分析結果を元に、一番上にキャンペーンバナーを持ってきましょうとアドバイスします。こういったカスタマージャーニーも記録・分析しています。
石井:
なるほど、そこまで把握できるのですね。我々が目指しているのは、顧客の労力を出来る限り減らすことです。応対内容だけでは難しく、行動パターンを含めると、実現できるのではと思っています。顧客の行動を遡り、できるだけ早い段階でお客さまを解決へ導くことです。解決していないが電話をするのが面倒くさい、という不満を抱えたまま離れていくお客さまを救い上げる仕組みを作る、企業のCXの根幹部分をお手伝いしていきたいと考えています。
しかし、BPOさんや現場の担当者にはなかなか響いていません。
古賀氏:
皆さん感じていると思いますが、サイロ化の構造が問題です。サイロ化が進むと自分の管轄だけ考えていればよい、ということになってしまいます。
海外では、CMO(Chief Marketing Officer)やCCO(Chief Customer Officer)などCxO(Chief x Officer)という横断的なポジションが生まれています。日本でもこの文化が広がると良いですよね。
※ カスタマージャーニーオーケストレーション:カスタマージャーニーに沿って、最適な次のステップにつながるパーソナライズされた体験を提供するプロセスです。 このプロセスは、堅牢な顧客データ、深い分析、人工知能(AI)に依存し、スマートジャーニーデザインの一部として次の最適なステップを予測します。
生成AIが全面的にユーザー対応する時代へ向け、ナレッジ整備が不可欠。世界的CE企業のベリントシステムズとモビルスが対談【後編】へ続く









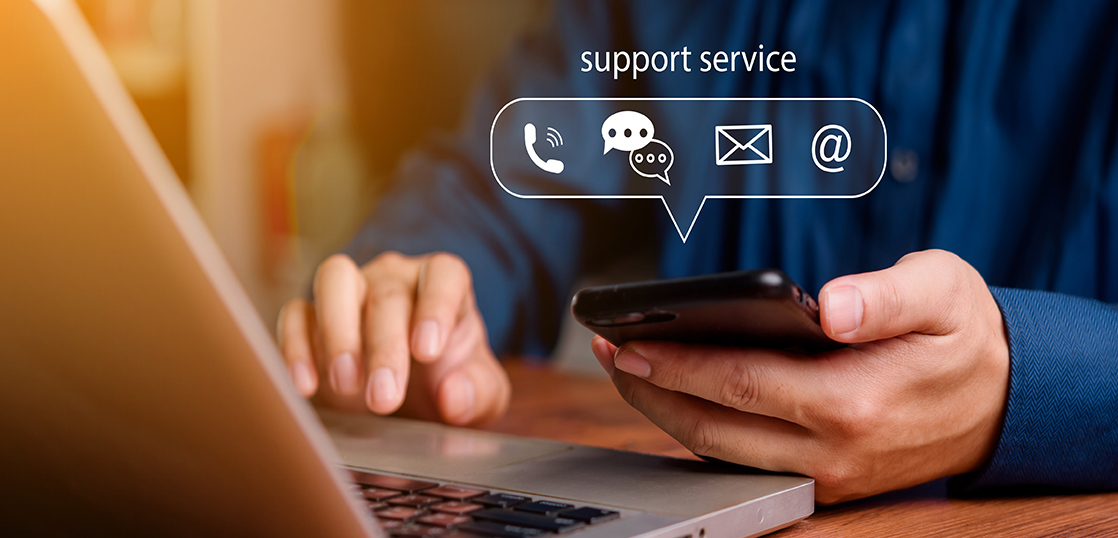

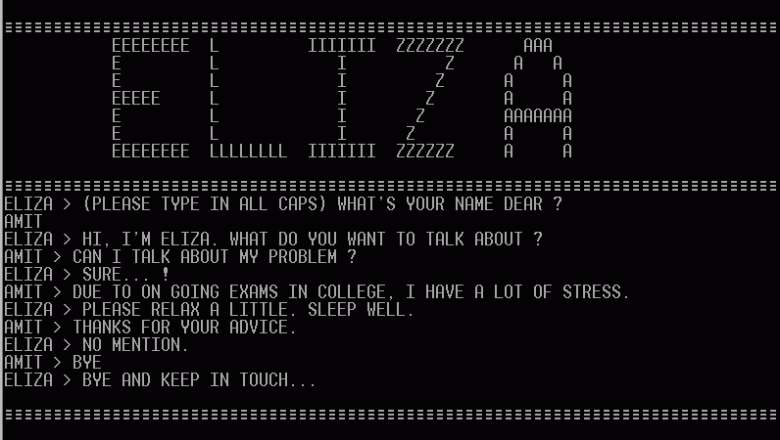

_web.jpg)