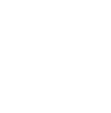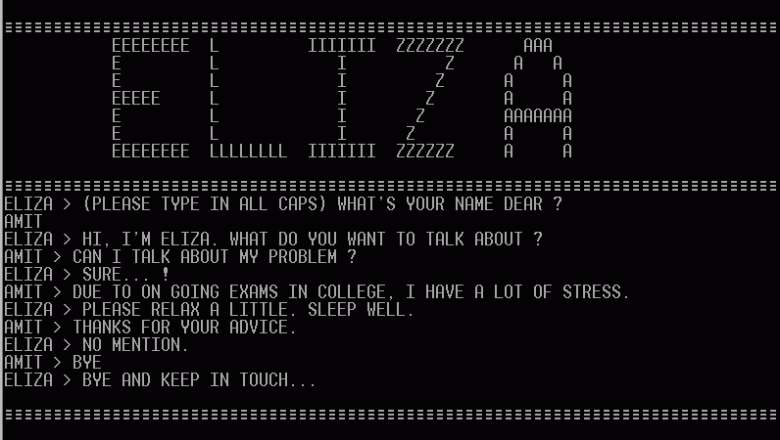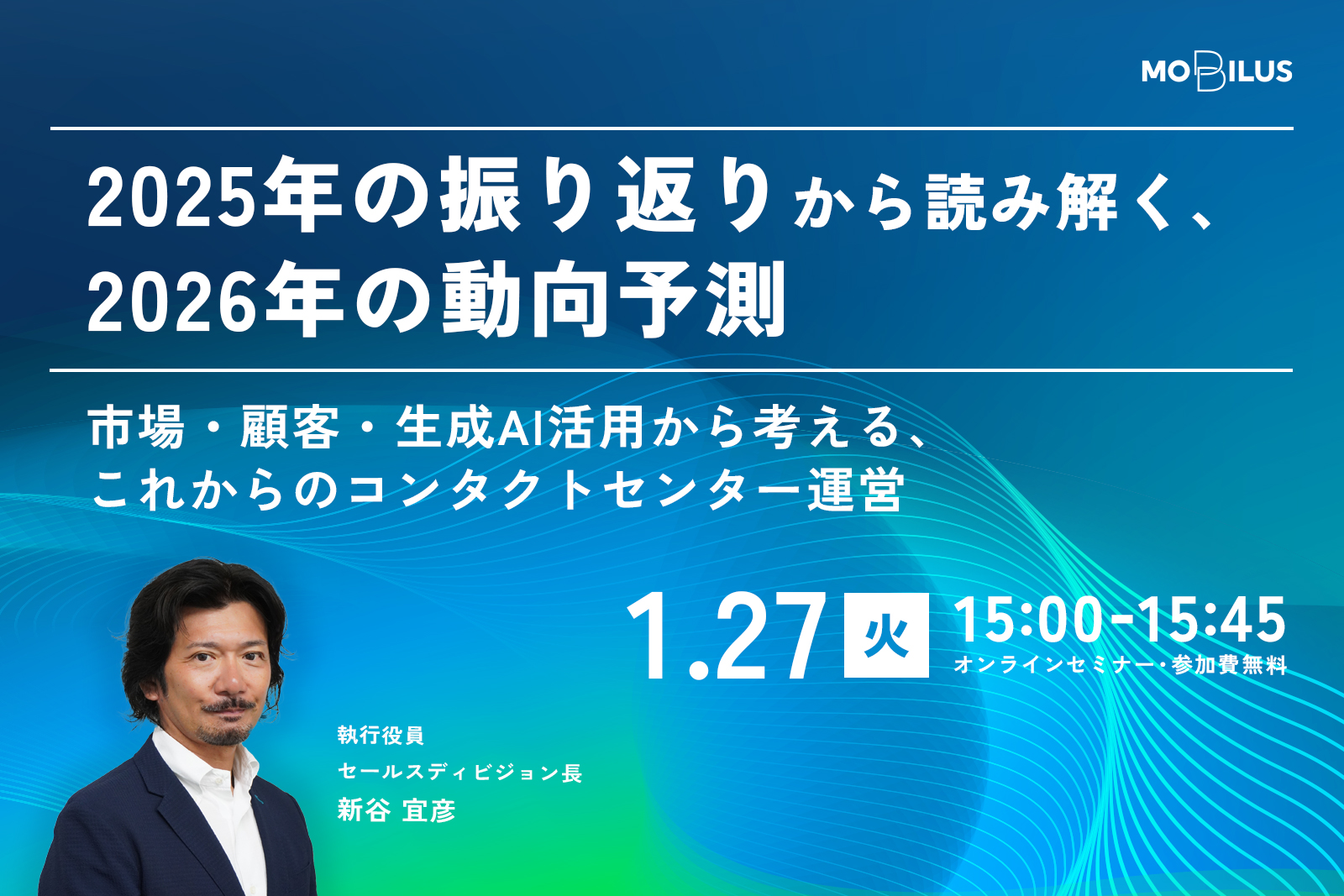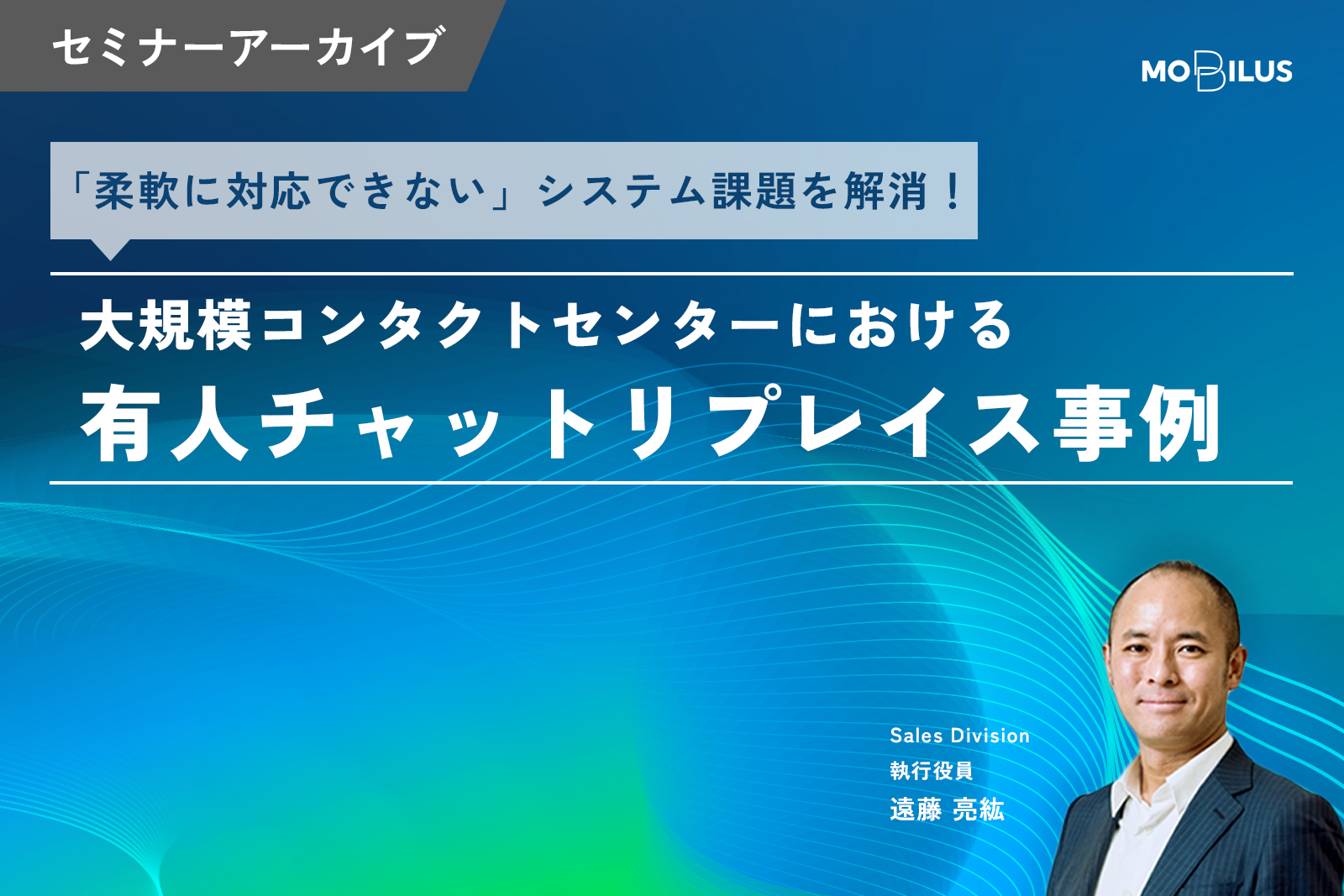チャットボット導入後の課題と解決策、効果を出す運用方法と運用サポート
投稿日:2025年8月22日 | 更新日:2025年8月29日
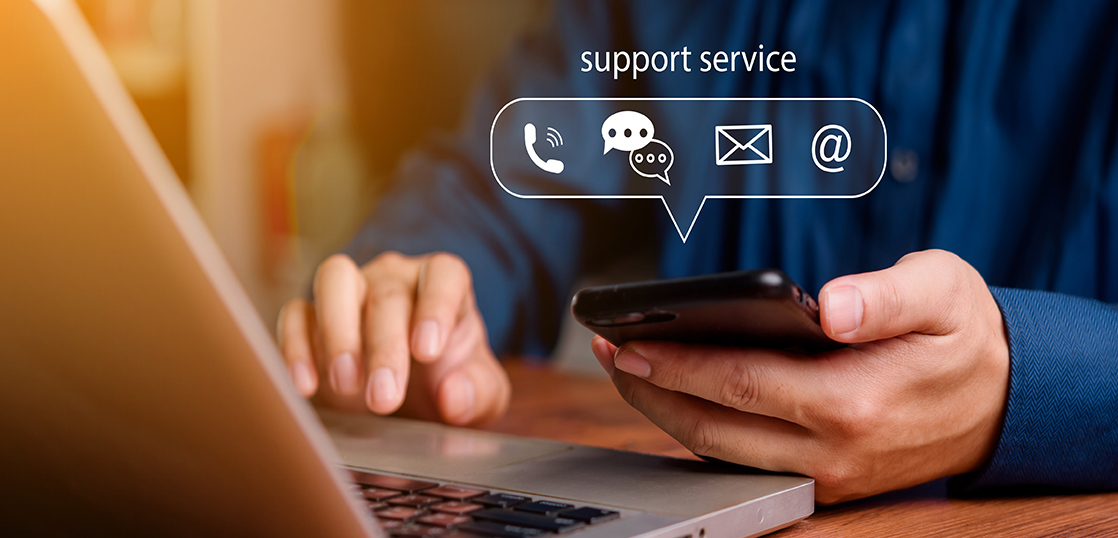
コールセンター(コンタクトセンター)をはじめとした顧客対応を行う窓口で、自動化による業務効率化や顧客体験(CX)の向上を目的にチャットボットを導入する企業が増えています。一方で、チャットボットを導入したものの、「効果が出ているかわからない」「チャットボットの利用率が低い」「メンテナンスに手が回らない」などといった運用後の課題をお持ちの方も多いのではないでしょうか。当記事では、チャットボット導入後によくある課題や解決策、効果を出す運用方法や運用サポートを中心に解説します。
<目次>
チャットボットの導入効果
はじめに、チャットボットの導入により得られる効果について見ていきましょう。主な導入効果は、以下です。
・顧客満足度の向上
・問い合わせ対応業務の効率化
・応対品質の均一化
・売上の向上
・データの効率的な収集
顧客満足度の向上
チャットボットは24時間365日対応可能なため、顧客は夜間や休日なども含め、好きなタイミングで問い合わせができます。電話で問い合わせをする場合、「つながらない」「待たされる」といったことが起きやすく、不満を生みやすいです。チャットボットであればすぐに回答を得られ、自己解決に導いてくれるため、つながらない不満の解消に効果的です。
なお、チャットボットで解決が難しい問い合わせも、有人チャットと連携されていると、チャット上でスムーズに解決まで導けるため、さらなる顧客満足度向上が期待できます。
問い合わせ対応業務の効率化
チャットボットの利用シーンとして、簡単な問い合わせへの自動応答、一次対応の受付や定型的な手続きの自動化などがあります。自動化により対応時間や業務負荷を削減できるほか、大量の問い合わせへの対応や単調業務から発生するストレスの軽減により、従業員の仕事に対するモチベーション向上や離職率低下に効果的です。
同じ内容の質問に繰り返し対応することや、定型的な手続き対応をチャットボットによって自動化できるため、問い合わせ業務の効率化を実現しやすい特徴があります。
応対品質の均一化
有人対応の場合、知識や経験の差により回答のばらつきが出てしまう場合があり、顧客満足度の低下にも影響を及ぼします。
チャットボットで問い合わせ対応を自動化することで、応対品質を均一化できるため、顧客満足度の向上にも効果的です。また、チャットボットをナレッジとして活用することで、新人オペレーターの育成にも役立ちます。
売上の向上
ECサイトやランディングページにチャットボットを設置したり、LINE公式アカウントにチャットボットを導入することで、ユーザーからの問い合わせ数の増加につながります。夜間や休日も資料請求や申込手続きなど自動応で対応できるため、機会損失を防ぐことが可能です。
ホームページ上で新たな顧客接点として機能することで、コンバージョンの向上にも貢献します。チャットボットの設置でサポート体制を充実させると、顧客がいつでも問い合わせができ、課題を解決しやすくなるため、顧客利便性やCXが向上し、結果、売上の向上を期待できます。
データの効率的な収集
チャットボットは問い合わせ履歴を自動で蓄積していきます。どのコンテンツに質問が集まるか、ユーザーの検索キーワードは何かなどを履歴から分析することで、顧客の悩みやニーズの把握、商品サービスの改善を効率的に行うことが可能です。
蓄積されたデータは社内での活用も期待できます。オペレーター間でのナレッジマネジメントにも有効利用でき、知識や業務の属人化を防ぐだけでなく、研修コストの削減にも効果的です。

チャットボットの導入事例
LINE MUSIC株式会社
LINE MUSICでは、コンタクトセンターに寄せられる年間約2万通のメールの多くは利用者が自己解決できる内容である点、精度の高いチャットボット運用のために利用者動向のデータ分析など難易度の高い業務を効率的に行うことができる運用の仕組みの確立が課題でした。
こうした課題解消のため、シナリオ編集が誰でも簡単にでき、高度かつ使いやすい利用者動向などの分析機能がある「MOBI BOT」とモビルスが独自開発したAI学習支援機能「MOBI BOT CONSOLE」を導入しました。これにより、AIチャットボット運用と詳細な分析が自社内で可能になり、運用が効率化された結果、AIチャットボット利用者満足度が10%向上しました。さらにAIチャットボットとFAQサイトの連動により、問い合わせ発生からほぼリアルタイムでFAQサイトを更新できる環境が整備されました。FAQサイトの更新頻度の向上および内容が充実することで自己解決率の約20%改善を見込んでいます。
LINE MUSIC 導入事例を無料ダウンロード!
LINE MUSIC さまの事例紹介をまとめた導入事例PDFはこちらからもダウンロードいただけます。
チャットボット導入後によくある課題
様々な導入効果が期待できるチャットボットですが、運用開始後、次のような課題を抱える企業も少なくありません。
・効果が出ているかわからない
・チャットボットが利用されない
・チャットボットの離脱率が高い
・回答精度が低い
・チューニングやメンテナンスが進まない
効果が出ているかわからない
よくある課題の一つ目は、導入後の効果が出ているかわかりずらい点です。電話問い合わせ数の削減を目的にチャットボットを導入したものの、効果測定方法やKPIを適切に設定していないと導入効果の確認が難しくなります。
電話の削減や自動化促進による業務効率化などを目的にチャットボットを導入しても、計測可能な効果指標を導入していないと、効果の測定や改善ができません。そのため、チャットボットを導入する際に、導入の目的や効果測定の方法、KPIの指標を設定することが重要です。
チャットボットが利用されない
よくある課題の二つ目は、チャットボットが利用されない・利用が少ないことです。利用率が低いと効果が出ているか測ることが難しくなります。
利用されない原因として、「チャットボットの存在を知られていない」「使い方が浸透していない」「電話する方が早いと思われるなど利点が伝わっていない」、といったことが考えられます。
チャットボットの離脱率が高い
よくある課題の三つ目は、チャットボットの離脱率が高いことです。離脱とはチャットボットの用意した回答にたどり着く前に、利用が中断されてしまうことを指します。
チャットボットの利用率が高くても、離脱率が高いと顧客満足度の向上や自己解決率の促進にはつながりません。離脱する原因は、「欲しい情報にたどり着けない」「たどり着くまでに時間がかかる」「回答内容を理解できない」「回答精度が低く必要な答えをもらえない」「チャットボットで解決できる範囲が限られていて有人窓口へかけ直しが必要」などです。
一度利用して使えない・解決できないと判断されると、次回以降利用されなくなり、利用率低下を招く恐れもあります。
チューニングやメンテナンスが進まない
よくある課題の四つ目は、チューニングやメンテナンスが進まないことです。チャットボットは導入して終わりではありません。運用しながら、チューニングやメンテナンスを繰り返し、使えるチャットボットに育てていくことが必要です。
チャットボットの利用率や解決率、利用者の満足度など効果検証をしながら、導線の見直しや、回答できなかった質問に回答できるように回答精度を高める、質問頻度が高い項目を追加する、導線を見直すとなど定期的にメンテナンスをしていきます。
チューニングやメンテナンスが進まない理由には、担当者が不足しているなど運用体制が確立していないことや、効果検証を行うためのリソース不足やメンテナンス方法が分からないなどが考えられます。

効果を出すチャットボットの運用方法と運用サポート
次に、チャットボット導入後の課題を解決し、効果を出すためのチャットボットの運用方法について解説します。課題解決の運用ポイントは以下の六つです。それぞれ詳しく見ていきましょう。
・現状把握と課題の分析
・適切なKPIの設定
・チャットボットへの導線の改善
・チャットボットの回答精度の向上
・有人チャットや他システムとの併用
・運用サポートの活用など運用体制の見直し
現状把握と課題の分析
まずは、チャットボットの利用率や解決率、チャットボット利用後の有人オペレーターによる対応数などを分析し、現状の課題を把握することから始めます。課題を把握することは、どこから改善すべきか、優先順位を考える上でも有効です。
チャットボットの導入前後で、問い合わせ窓口全体の変化を見える化することも大切です。たとえば、問い合わせの総数、解決率、オペレーターの稼働時間、応答率など指標を設定し、チャットボット導入による変化を見える化することで、「効果が出ているかよく分からないから運用を停止する」といった事態を回避できます。
適切なKPIの設定
効果が出ているか測定するためにも、あらかじめ適切なKPIを設定することが重要です。
たとえば、下記のような指標があります。
起動数:チャットボットが起動された数
対応件数:ユーザーがチャットボットを使った数
解答率:チャットボットが質問に回答した数
正答率:チャットボットが正しい回答を示した数
解決率:回答に満足したユーザーの割合(チャットボットでアンケートを実施)
サイト推移数:チャットボットが案内したWebページにアクセスした数
問い合わせ数:有人窓口への問い合わせ数(エスカレーション数)
コンバージョン数:設定したコンバージョンを達成した数
チャットボットへの導線の改善
チャットボットの利用率が低い場合、存在を認知させることが必要です。Webサイトのトップページへの表示や、ポップアップ表示など、目に付きやすい場所への設置や、サポートページや購入画面など問い合わせが必要なタイミングで表示させるなど、導線を改善することで認知を広げることができます。
また、導線改善とともにチャットボットのUI設計の見直しも重要です。たとえば、目立つデザインにしたり、親しみやすいキャラクターを設定したり、使い方を説明する文言の設定などが改善方法として考えられます。
<合わせて読みたい記事>
チャットボットの回答精度の向上
チャットボットが利用されても、欲しい回答をすぐに得られないと感じさせると離脱につながりやすいです。チャットボットの平均正答率は、60~80%と言われています。最初から100%をめざす必要はなく、運用しながら正答率を高めていくことが大切です。
回答精度向上の方法として、シナリオ型チャットボットの場合は、シナリオ設計の見直しをすることや、機械学習型チャットボットの場合は、AIの学習データの定期的なメンテナンスが挙げられます。また、「なんでも答えるチャットボット」だと回答にたどり着きにくい場合も多いです。チャットボットが回答する範囲を見直し、問い合わせの目的に沿った専門のチャットボットを作ることも有効です。たとえば、購入ページには購入に関する質問に答えるチャットボット、会員向けページには注文状況の確認や配達状況確認のチャットボットを設置するなどです。
有人チャットや他システムとの併用
チャットボットだけで、すべての問い合わせ対応を完了できるわけではありません。チャットボットで解決できない場合に、有人窓口や他システムへ連携できる導線を作っておくことも重要です。
たとえば、有人チャットと連携することで、チャットボットが一次受付や定型的な手続きを自動化し、個別対応が必要なケースは有人チャットへスムーズに引き継ぐことができると、顧客の満足度向上や業務効率化に有効です。
また、問い合わせ内容に応じて、有人チャット、コールセンター、FAQシステムなど、適切なチャネルへ振り分ける役割をチャットボットが担うこともできます。
運用サポートの活用など運用体制の見直し
運用体制に不足があると、分析や改善、定期的なメンテナンスが進まない要因となります。チャットボットを運用するチーム体制を構築する、一人に任せて属人化しないよう複数人にするなど仕組み作りが必要です。
また、最初から社内で自走化が難しい場合もあるため、KPIの設定や分析方法などチャットボット導入前後の運用サポート体制の有無を確認しておくと良いでしょう。外部の運用サポートを活用しつつ、自走できる体制を構築していくこともおすすめです。
チャットボットの有効な運用サポート
「効果が出ているかわからない」「チャットボットの利用率が低い」「メンテナンスに手が回らない」などは、チャットボット導入後によくある課題です。こうした課題を解決し効果の出るチャットボット運用を行うためには、「現状把握と課題の分析」「適切なKPIを設定する」「チャットボットへの導線を改善する」「チャットボットの回答精度を上げる」「有人チャットや他システムとの併用」「運用サポートの活用など運用体制の見直し」が有効です。
チャットボットは導入して終わりではなく、運用しながら改善していくことが欠かせません。当記事を執筆したモビルスは、プロアクティブなサポートで企業を成功に導くため、CXを向上させる伴走型のサポート体制(カスタマーサクセスメニュー)を整えており、チャットボット導入前のシナリオ構築から、運用後の回答精度向上・KPI分析・利用促進・定着化まで全フェーズを支援するサービス提供をしています。ぜひご相談ください。
チャットボット「MOBI BOT」紹介資料
モビルスの「MOBI BOT(モビボット®)」は、サポートはもちろん顧客体験までつくるチャットボットです。機能、解決できることなどを紹介資料にて掲載しています。
下記より、ダウンロードいただけます。ぜひご覧ください。
顧客体験を最大化するCX戦略支援 CX Consulting
モビルスでは、クライアントの顧客体験を最大化するため、カスタマージャーニーマップ作成や定量的調査を通じたCX戦略立案・策定を支援しています。解決するお悩みや、CXコンサルティングの流れ等の詳細は、以下からご覧ください。