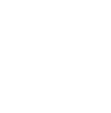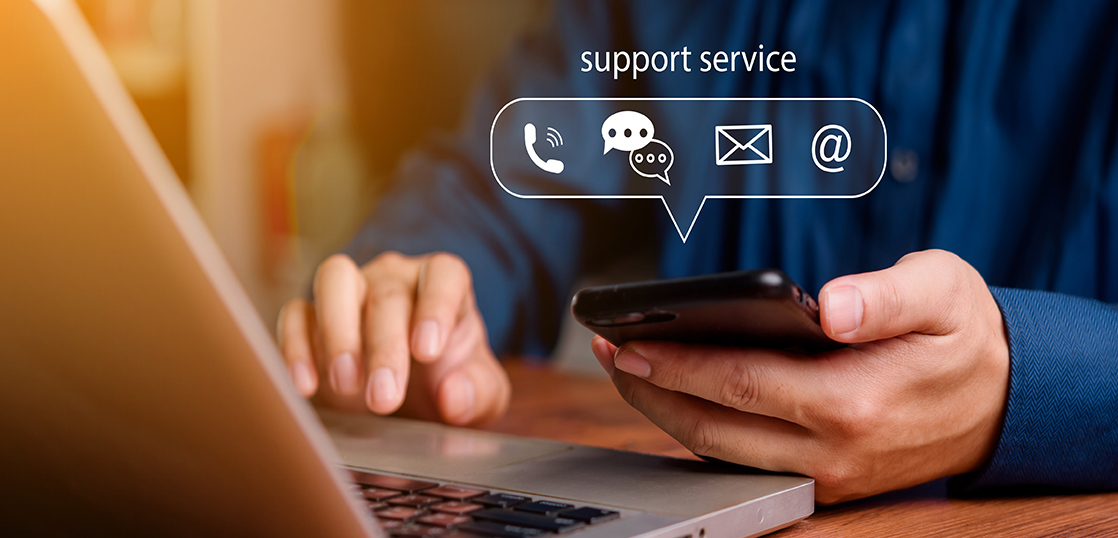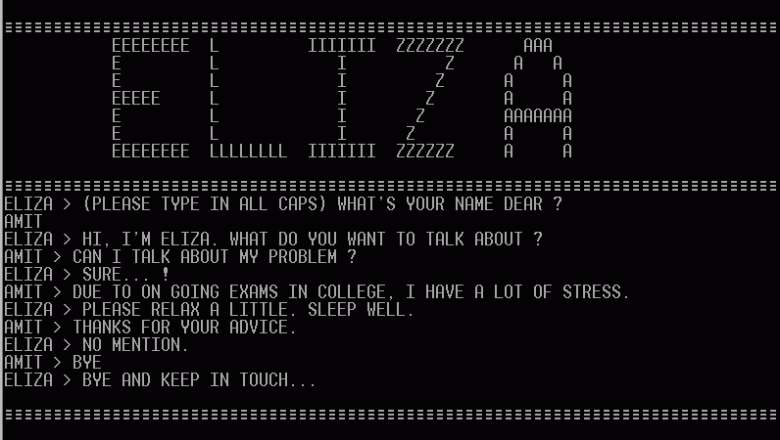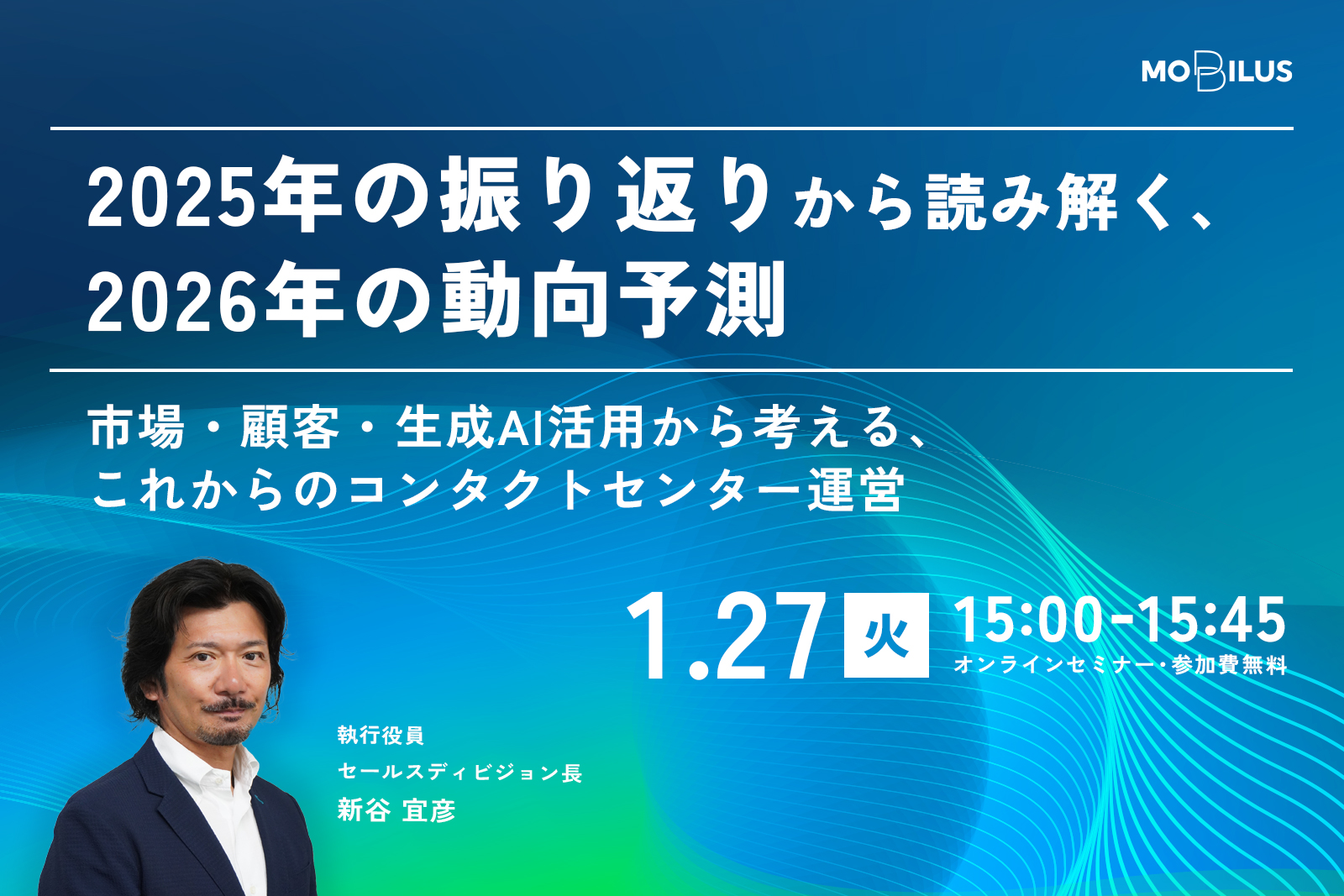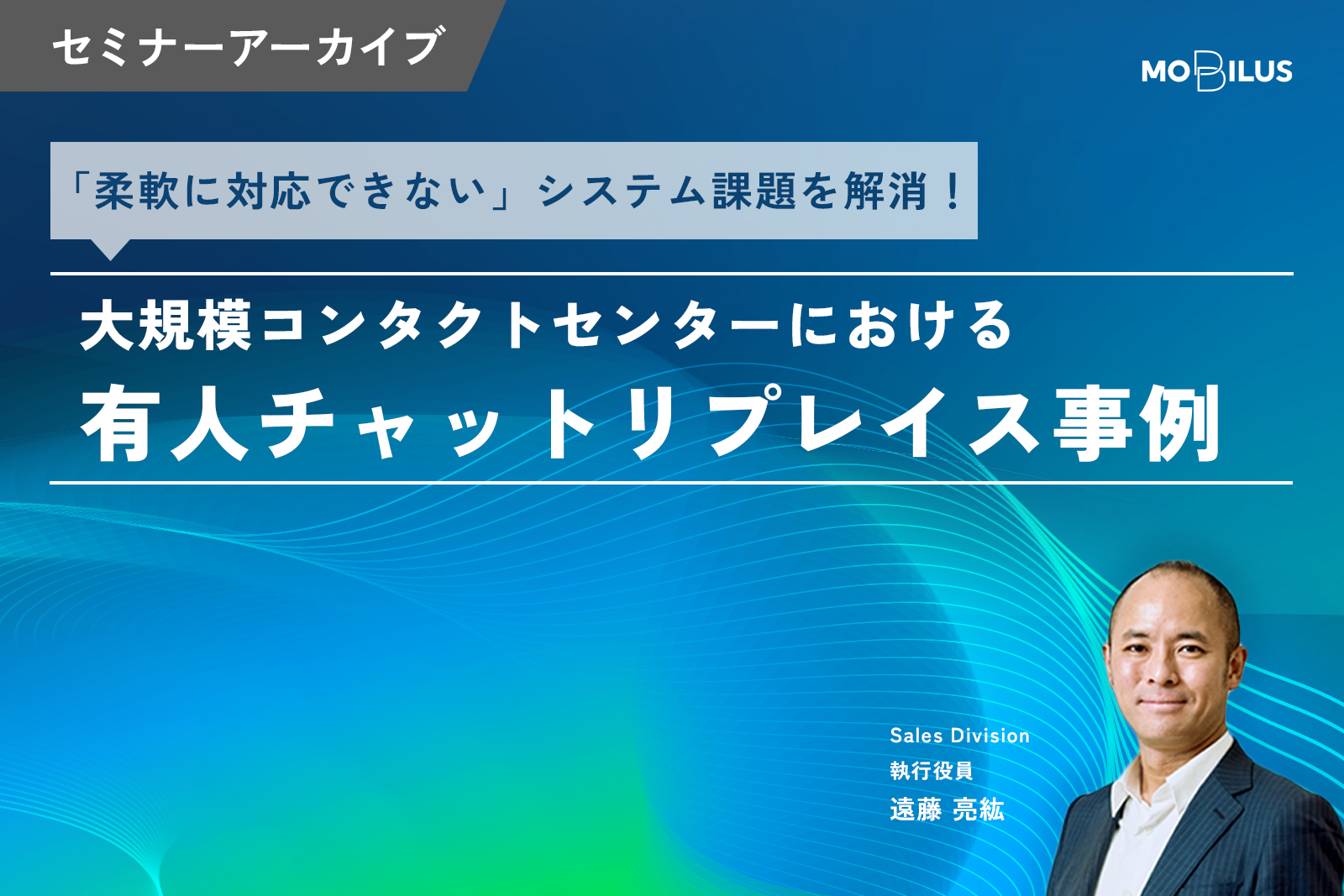チャットボットの「利用率」が低い理由・向上のための設計術とは?
投稿日:2025年8月29日 | 更新日:2025年8月28日

企業のカスタマーサポートにおいて、チャットボットはユーザーの疑問を解決する重要な窓口です。しかし利用率の低いチャットボットは、期待する業務効率化やコスト削減につながらないだけでなく、かえって顧客満足度を低下させてしまう可能性もあります。
本記事では、チャットボットの利用率を重視するべき理由から、利用率が低くなる原因・それによって起こる問題と、改善するための具体的な設計術まで解説します。
目次
チャットボットの「利用率」が重要な理由とは?
ここでは、チャットボットの活用において、なぜ「利用率」が重要な指標とされるのかを解説します。
チャットボットは、企業のカスタマーサポートやFAQ対応を自動化するための有力なツールとして広く導入されています。しかし、「導入したものの、ユーザーに使ってもらえない」というお悩みは、チャットボット導入が進んだ今なお、多くの企業から耳にします。
チャットボット活用において重要なのは「導入率」と「利用率」を分けて考えることです。導入率が、サイトやアプリにチャットボットを設置した企業の割合を指すのに対し、利用率は実際にエンドユーザーがチャットボットを使ってくれた割合を意味します。どれだけ優れたチャットボットを導入しても、ユーザーに利用されなければ、業務効率化や顧客体験(CX)の向上といった導入メリットは生まれません。そのためチャットボットの導入効果を測る上で重要な指標となるのが「利用率」なのです。
チャットボットの利用率が低いことで生じる問題とは?
次に、チャットボットの利用率が低い場合に起こりうる、三つの問題について見ていきましょう。

問い合わせ対応コストが削減できない
多くの企業がチャットボットに期待するのは「問い合わせ対応業務の効率化」ではないでしょうか。特にカスタマーサポート部門では、問い合わせの大半が「FAQ(よくある質問)」や「手続き案内」といった定型的な内容で占められています。
しかし、チャットボットがユーザーに使われない状態では、結局すべての対応が有人チャネルに集中してしまいます。つまり「導入しただけ」ではコストは削減されず、むしろ問い合わせ対応にかかる負担が二重になるケースも珍しくありません。
「自己解決できない」ことが顧客体験(CX)の低下につながる
近年では、差別化要因として顧客体験(CX※1)の重要性が高まっています。顧客(ユーザー)は「待たされる問い合わせ」を嫌い、自分で情報を探して素早く解決することを好む傾向にあります。チャットボットが活用されない場合、こうした自己解決の導線が不十分になってしまう可能性があります。
「情報を探したけど、結局電話するしかなかった」「チャットがあるのに、何も答えてくれなかった」「質問してもピント外れな回答ばかりで、時間の無駄だった」こうしたネガティブな体験が積み重なると、ユーザー体験(UX)の低下が起こり、ひいては顧客体験(CX)の低下につながってしまいます。その結果、この企業は不親切、二度と使いたくないといったブランドイメージの毀損に直結します。特に競合とサービス内容が似ている場合は、カスタマーサポートにおけるCXそのものが、顧客(ユーザー)に選ばれる理由、あるいは離脱する理由になることも考えられます。
※1 CX(Customer Experience):顧客がブランドや企業との全ての接点を通じて得る体験の総体。製品やサービスの利用だけでなく、問い合わせ対応や情報の探しやすさなど、あらゆる接点がCXを形成します。
ユーザー(顧客)データが蓄積されない
チャットボットは、単なるFAQ自動化ツールではなく、ユーザー(顧客)のインサイトを収集するための貴重な情報源にもなります。「どんな言葉で悩みを入力しているのか」「どの段階で離脱しているのか」「どの質問に対して満足しているのか」といったログを分析することで、サービスやFAQの改善点が見えてきます。たとえば、「クーポンに関する質問が増えている」なら、キャンペーン設計や導線の見直しにもつながるでしょう。
しかし、そもそも利用されていないチャットボットにはログが残りません。つまり、改善のためのPDCAを回す土台すら失われている状態です。これはただの機会損失ではなく、将来的な競争力低下にもつながる重大な問題といえるでしょう。
チャットボットの「利用率」が低い理由とは?
続いて、チャットボットの利用率が上がらない原因として考えられる、ユーザー体験(UX)の課題が挙げられます。UXの課題について詳しく見ていきましょう。

ユーザーが存在に気付いていない
多くのチャットボットは、PCやスマホ画面の右下に小さく表示されていることがほとんどです。ユーザーがコンテンツを読むことに集中している場合、その存在に物理的にも認知的にも気付かないことがあります。さらに問題なのは「目に入っても無視されている」ケースです。
- 画面に突然出てくるため、広告やポップアップと誤認される
- 見た目が無機質すぎて興味が湧かない
- チャットが開くと大きくて邪魔だと感じる
これらは、設置場所だけでなく、アニメーション、アイコン、色、初回メッセージの設計を総合的に見直さない限り、なかなか改善されません。
使い道がわからない
チャットボットに「こんにちは!お困りごとはありますか?」とだけ表示されても、ユーザーは何をどう質問すれば良いのか分からないものです。これはいわば「ガイドのいない受付機」です。目的がはっきりしないものには、ユーザーは関わろうとしません。
具体的に伝えるべきことは
- どんなことを解決できるか(例:予約変更・注文状況の確認など)
- どのように質問すればいいか(例:自然文OK/キーワード入力など)
- 所要時間や手間(例:最短30秒で解決、3ステップで完了)
といった内容です。
UXが悪い(操作しにくい・入力しにくい)
スマートフォンユーザーの割合が年々増加している中で、「使いづらいチャット」はそれだけで離脱要因となります。
- 入力欄が小さい、ボタンが押しにくい
- 選択肢の表示が折り返されて読みにくい
- 誤操作で戻るボタンを押すとチャットが初期化される
- エラーメッセージが不親切(例:「不明なエラーです」)
こうした細かなUX※2の欠陥は、ユーザーがチャットの利用をためらう原因となります。特に電話やメールといった他の問い合わせ手段が用意されている場合、そちらに流れてしまう可能性が高まります。
※2 UX(User Experience):製品やサービスを通じてユーザーが得るすべての体験を指します。チャットボットにおいては、チャットの立ち上げから問題解決に至るまで、一連の流れがスムーズであるかが重要になります。
回答の精度が低い
チャットボットが以下のような「見当違いの回答」を返すと、ユーザーは「このチャット、使えない」と判断します。一度でもネガティブな印象を与えると、その後の利用につながらない可能性が高くなります。
- 回答の文脈がズレている(例:「返品について」と聞いたのに「配送の遅延情報」を出す)
- 同じ質問をしても異なる回答が返ってくる
改善にはFAQの充実、対話ログの分析、自然言語処理の精度向上が不可欠ですが、そもそも“なぜそれを改善すべきか”が現場に伝わっていないケースも多く見られます。
有人対応に切り替わらない
ユーザーは「チャットボットで解決できなかった場合、有人対応に切り替わるだろう」と少なからず期待しています。それが叶わないことは、機能そのものよりも企業の姿勢への不信感に変わっていきます。有人対応へのスムーズな切り替え(ボタン一つでOK/時間帯に応じた案内)を用意していなければ、ユーザーにとって「行き止まりのUX」になってしまうのです。
チャットボットの利用率を高める方法とは?
チャットボットの利用率を高めるには、UXを第一に考えた設計が不可欠です。ここではその方法を、具体的な例を挙げてご紹介します。

導線は「置く場所」ではなく「出すタイミング」で設計する
チャットボットを単に画面の右下に配置するだけでは、ユーザーに利用されないことが増えています。現代のユーザーは、それが広告か重要な機能かを1秒で判断し、「ノイズ」だと感じたものは無視します。
ではどうすればいいか?答えは、ユーザーの行動文脈に応じてチャットを「出現」させることです。
具体的には以下のような設計が効果的です。
- 商品ページで60秒以上滞在しているユーザーに「在庫でお困りですか?」とポップアップ
- フォーム入力を中断したユーザーに「記入方法で不明点がありますか?」とアプローチ
- カート放棄が多い画面で、「配送日・送料など、よくある質問はこちら」と表示
チャットボットを「呼び出されるもの」ではなく、「必要な時に現れる存在」にすることで、自然な利用の流れが生まれます。
初回発話は「問い」ではなく「提案」する
「何かお困りですか?」という曖昧な問いは、ユーザーに思考の負荷をかけ、逆に行動を止めてしまいます。有効なのは、ユーザーの目的を先回りして提示する設計です。
たとえば、購入ページなら「返品・交換のルールをご案内しましょうか?」「クーポンコードが適用されない場合の対処法はこちら」といった形です。このように「選ばせる選択肢」ではなく、「導く提案」を行うことで、ユーザーの心理的ハードルを下げ、対話のきっかけを作ることができます。
「入力させる」のではなく「操作させる」
ユーザーがチャットを避ける最大の理由は、「どう質問すればいいかわからない」「打ち込むのが面倒」というUX上のストレスです。これを軽減するために、選択肢型の操作体験を基本にすることが有効です。
具体的には
- 「注文状況を知りたい」「返品方法を調べたい」といったボタンを表示し、自由入力は2ステップ目以降にする
- 入力欄に「配送 遅延 などと入力してください」と例を出す
- タップしやすいサイズ・スペース・色を意識してスマホ最適化を行う
などが挙げられます。
「答えの正しさ」よりも「解決までの距離」を短くする
FAQが充実していても、ユーザーが「結局わからなかった」と感じれば意味がありません。大切なのは、「回答したか」ではなく「ユーザーの課題が解決したか」という視点です。
たとえば「返品できますか?」という質問に対して、「はい、返品は可能です。こちらのフォームからお手続きいただけます」と、実行アクションまでの導線を設計することで、答えを「情報」で止めず「完了」まで導き、チャットボットは「また使おう」と思える存在になります。
まとめ
今回は、チャットボットの「利用率」に着目し、その重要性、利用率が低いことで起こる問題、そして具体的な改善策までを解説しました。
チャットボットは、ただ導入するだけでは期待する効果を得ることはできません。利用率が低い状態が続くと、コスト削減が進まないだけでなく、顧客満足度の低下や貴重なユーザーデータ収集・分析の機会損失にもつながりかねません。
しかし、これらの課題は、チャットボットの設計を少し見直すだけで大きく改善できます。「いつ、どのように表示するか」という導線や、ユーザーに「入力」ではなく「操作」させるUXを意識することで、チャットボットはユーザーにとって「使える」存在へと変わります。
チャットボットは、使い方を工夫することで、コスト削減とCXの向上という二つの目標を同時に達成できる強力なツールです。チャットボット導入・運用でお困りの点がありましたら、ぜひ一度ご相談ください。
定型業務の自動化でCX向上を実現する「MOBI BOT」製品資料
問い合わせ対応から手続き処理を自動化できるチャットボット「MOBI BOT(モビボット®)」の製品資料です。有人チャット「MOBI AGENT(モビエージェント®)」との連携で顧客満足度向上につなげます。MOBI BOTは、大手企業を中心として、金融・メーカーから自治体まで、幅広い業種のお客さまにご利用いただいています。
チャットボット・セルフチェックシート
モビルスでは、これまでのチャットボット導入・運用支援で培ったノウハウをもとに独自のセルフチェックキットをご用意しました。チャットボットを多面的に自己診断できる「セルフチェックシート」とチャットボットの改善に役立つ「項目別ポイント解説」が含まれています。無料でダウンロードいただけますのでご活用ください。