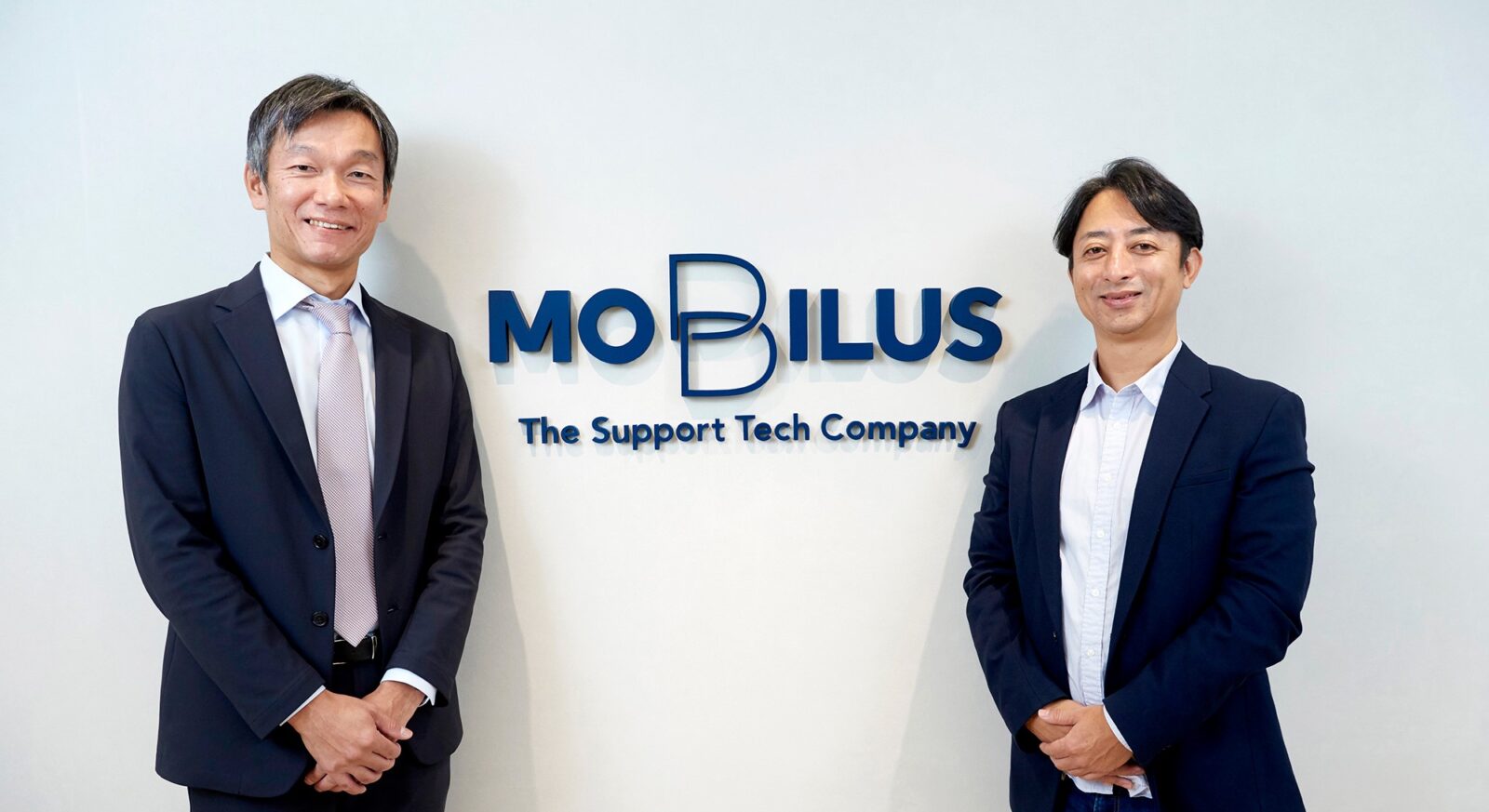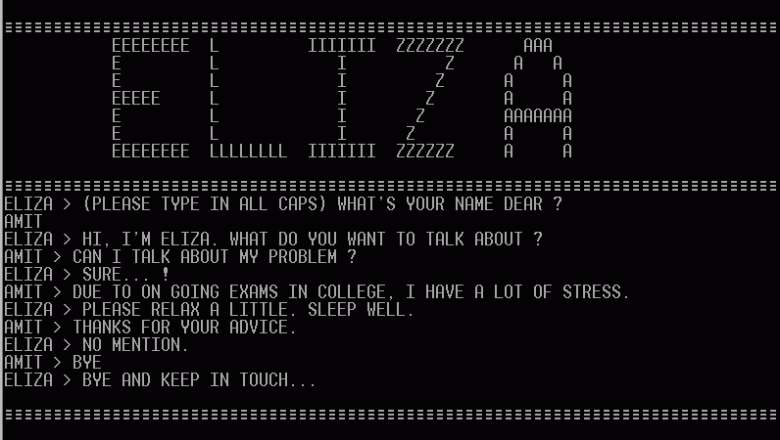生成AIがもたらすコンタクトセンターへのインパクト~アドバンスト・メディア×モビルスが考える、生成AIによる顧客体験の変革とは?~
投稿日:2023年11月13日 | 更新日:2023年11月13日

「顧客体験の変革: 生成AIがもたらすコンタクトセンターへのインパクト」をテーマに、音声認識技術AmiVoice(アミボイス)を使ったソリューションの開発・提供を行う株式会社アドバンスト・メディア 取締役 大柳 伸也 氏と、顧客サポート業務のソリューションの開発・提供を行うモビルス株式会社 代表取締役社長 石井 智宏が対談を行いました。
技術の進化と業界のトレンド、ユーザー企業の動向、生成AIの利用シーン、活用にあたっての課題、両社の今後を見据えた取り組みについて対談した模様をお届けします。
■対談メンバー
株式会社アドバンスト・メディア 取締役 大柳 伸也 氏
2008年株式会社アドバンスト・メディア入社、コンタクトセンターおよび製造物流現場での音声認識システムの市場化に従事。2013年CTI事業部長に就任し、パートナー企業との連携強化に努め、コンタクトセンターにおける業務効率化・データ活用・応対品質向上など、人工知能を用いた新たな価値を創造、2018年より事業本部長として国内事業を統括。国内ビジネス領域における多種多様なサービス拡大に加え、2019年12月には音声認識プラットフォームを立ち上げ、「昨日のありえないを、明日のあたりまえに」があふれる世の中の実現に向けて事業推進中。
モビルス株式会社 代表取締役社長 石井 智宏
1998年 早稲田大学卒、2009年 ペンシルベニア大学ウォートンMBA取得。ソニー株式会社にて11年間ラテンアメリカ市場におけるセールスマーケティングに従事。MBA取得後、国内投資ファンドにて執行役員。その後ソニー会長率いるクオンタムリープ株式会社のエグゼクティブパートナーとして多数の日本企業の海外進出を実行支援。2014年モビルスに参画。受託開発中心のビジネスから業態チェンジをし、主力製品「MOBI AGENT」や「MOBI BOT」「MOBI VOICE」などをリリース。企業のコンタクトセンターや自治体向けに製品の提供、導入支援を行っている。
「AI」を切り口に、コンタクトセンターの業務効率化・CX向上を目指す
―はじめに、両社の事業概要をご紹介ください。
大柳氏
アドバンスト・メディアは26年間、音声認識の会社として活動しています。基本的に音声認識は「声を文字に変換する技術」なので、コンタクトセンターや議事録作成を必要とする自治体や民間企業、医療の現場、商談シーンなど、声のあるところに我々のビジネスチャンスが存在します。
他にも、製造、物流、不動産、建築などの現場向けのサービスを展開しています。最も事業規模が大きいのはコンタクトセンターで、全体の40%ほどを占めています。

コンタクトセンター向けには2003年頃からビジネスを開始し、今年で20年になります。
当初はコンプライアンス観点のもので、エビデンスが重視される金融関係にニーズがありました。当時は録音を行っていない企業もありましたが、録音を行っても目的の箇所を見つけることが困難なため「テキスト化して見つけやすくしたい」というニーズがあったのです。その後、「顧客満足度」「CX」というキーワードが登場し、現在はAIと関連付けて効率化していきたいというニーズも増えてきています。
また、医療、介護、看護、調剤薬局などの医療現場でも音声認識を活用いただいておりますし、工場や倉庫などの作業現場では「点検して入力」「作業して入力」というように入力頻度が高いため、このような作業現場向けのサービスでは「ハンズフリー」「アイズフリー」「ペーパーフリー」そして「ストレスフリー」の、4つのフリーをコンセプトにサービス展開を行っています。
石井
モビルスは企業の顧客タッチポイントの最前線である接点、例えばコンタクトセンターなどで使われるソリューションの提供を行っています。
特にテーマとして2つのテーマを掲げています。1点目は「ボイスからノンボイスへ」です。テキストベースのコミュニケーションで顧客接点を作っていくことに挑戦しています。2点目は、ボイスを含めて「人から自動化、人からシステムへ」で、人が効率的な対応をするための自動化ツールや支援機能などを提供しています。
その根底にあるのは「オペレーションに組み込まれる要素にきちんと向き合い、お客様のニーズもしっかりと拾い上げた形で使える製品を作ること」「作った後も使ってもらえるところまで支援すること」です。
弊社に限らず業界全体に言えますが、最近の流れは、生成AIという大隕石にどう向かい合っていくのか、どういうところで開発を進めていくのか、そしてソリューションにどう組み込んでいくのか、というテーマと向き合っています。
生成AIは単なるブームではなく、トレンド転換である
―生成AIをはじめとする技術の進化と業界のトレンドについてどうお考えでしょうか。また、それを踏まえて、コンタクトセンター業界はどのように変化するのでしょうか。

石井
よく「生成AIによって最もインパクトを受ける業界はコンタクトセンターだ」と言われます。ソリューションベンダーはもちろん、特にBPOベンダーは自分たちの事業モデルが変わっていく危機感を持っており、非常に加速した取り組みが始まっていると思っています。
海外に比べてこれまで日本はAI活用が遅れていましたが、生成AIのインパクトによって急激に変化していくのではないかと感じています。
今までも日本では2014年ごろに第三次AIブームと呼ばれるディープラーニング技術を中心としたAIブームがありました。ただ、第三次AIブームでは、大型のデータセットを作る必要があるなど、ユーザー企業側で労力をかける必要があり、期待値を超えるような結果(ROI)が出せず、2~3年ほどでブームは終息しています。
それに比べると今回の生成AIはユーザー企業の負担が軽く、APIを利用するだけでレスポンスが返ってくるということをユーザー企業自身も実体験しているところが大きな違いとしてあります。ユーザー企業としても、「これを使えば他社に頼ることなく自分たちで効率化できるのではないか」といった意識も出てきていると感じます。そうした相乗効果で急速に変化していくのではないかと思います。
大柳氏
第三次AIブームで注目されたプロダクトを見ると、データセットを作成する労力に加えて、コストがかかるところもネックだったと思います。そのため、一般の消費者では使えませんでした。ただ、今回の生成AIはChatGPTに登録さえすれば、誰でも無料で使えます。使うためのハードルが低く、使ってみることで、仕事でどう活かせるかというイメージもしやすくなったため、広がりやすいのではないかと思います。
よくキャズム理論※の話をしているのですが、今のChatGPTや生成AIは、アーリーアダプターの位置にいるのだろうと思います。ただ、アーリーアダプターとアーリーマジョリティの間には大きなキャズム(溝)があるので、そこを超えなければ大きく飛躍しないと言われています。
※ キャズム理論:キャズム理論は、ハイテク製品の市場浸透の過程を説明するモデル。市場を5つのユーザーグループ(イノベーター、アーリーアダプター、アーリーマジョリティ、レイトマジョリティ、ラガード)に分類し、製品がどの層に受け入れられているかで浸透度を測る。キャズムはアーリーアダプターとアーリーマジョリティの間に位置し、その製品が市場に普及するために超える必要のある溝を示している。
石井
確かに音声認識はキャズムを超えましたね。超えたと実感したのはいつ頃ですか?

大柳氏
音声認識がキャズムを超えたと実感したのは、2019年、2020年頃かもしれません。参入企業が増えて、製品の価格競争が始まったことを実感したのが2019年、2020年頃です。
第三次AIブームの時に機械学習が行われるようになり、そこで一度盛り上がりましたが「精度が少し良くなった」という程度で終わってしまいました。それから働き方改革というキーワードが出てきて、我々も技術を研さんし、DNN(ディープニューラルネットワーク)やLSTM(Long Short-Term Memory: 長・短期記憶)、今はEnd-to-End(通信を行う二者を結ぶ経路全体、もしくはその両端)といった技術の向上も見られるようになりました。
コロナ禍も大きな要因だったと思います。ウェブ会議が広まり、今までは録音していないと取得できなかった音声が、TeamsやZoomによって簡単に取得できるようになりました。それを次々にテキスト化して貢献していく形ができるようになったのは、コロナ禍の初期となる2019年、2020年頃からなので、やはりその頃から市民権を得たという印象です。
コンタクトセンターの生成AI活用の主流とは
―これまでの両社の取り組みで最も進んでいる事例について教えてください。
大柳氏
ある通信会社大手のコンタクトセンターは熱心でした。同社はコンテンツのチャネルを持っていて、それは日々変化する類のものですが、自分たちで上手くメンテナンスをしてオペレーションを変えていきながら、オペレーターに対しての回答サジェストもリアルタイムで運用していました。
あと、音声認識だけではなく感情解析を使った「感情の見える化」についても取り組んでいる企業もいらっしゃいます。お客さまの感情についてはまだ活用が難しい部分がありますが、オペレーター側の感情を解析して、マインドが下がってきているなどをチェックし離職防止につなげることを行っています。将来的にはお客さまの解約防止に感情解析を生かせるようにできればと考えているようです。
石井
それはすごいですね。弊社ユーザーのメーカー企業の場合は、ノンボイスへのシフトを推進しており、既に7割以上の業務をノンボイス化しています。この取り組みを積み上げで実践され、結果的にはCPC※を半分以下に減少させています。
※CPC:Cost Per Call(コスト・パー・コール) の略。電話応対1通話にかかるコストのことを指す。
ノンボイスの有人対応については海外のオフショアでのオペレーションにシフトしています。日本語を話せるオペレーターが翻訳機能などを使わずに対応しており、オペレーターコストは日本で行う場合の3分の1です。オペレーターにとっても、日本語を使った仕事ができるというのでモチベーションは高く、採用活動もモチベーションが高く良い人材が応募してくるので、非常に上手く回っています。
ノンボイス対応が進んだため、次の課題として電話の滞留を解消する取り組みを行っております。まずは電話いただいたお客さまに自動音声で用件を確認し、一次回答をSMSで送信します。その内容で解決しなければ折り返し対応、あるいはチャットセンターにつながるLINEに遷移させて、リアルタイムに対応していく、ということを行っています。
―生成AIを活用して取り組んでいる事例や利用シーンなどについて教えてください。
大柳氏
コンタクトセンター以外ではサイネージでの案内や議事録の要約などで活用されており、ユーザー企業の声を聞きながら個別対応も行っています。
今後のコンタクトセンターにおいては、生成AIは応対履歴を自動生成することなどに落とし込まれていくのではないかと思います。今は電話の音声をテキスト化するのみですが、それを要約や応対履歴を作成し、更にそこからFAQを自動生成するような連携の方向性だと考えています。既に一部の顧客では試験的に行っているところもあり、期待値は相当高いです。議事録作成支援サービスでは、既存クライアントに対して要約まで自動的に作成される機能を無料で提供し始めました。ただ、実際に運用するとなると、セキュリティやハルシネーション※、コストの問題などが出てくると思います。
※ハルシネーション:人工知能(AI)が事実に基づかない情報を生成する現象のこと。まるでAIが幻覚(=ハルシネーション)を見ているかのように、もっともらしい嘘(事実とは異なる内容)を出力するため、このように呼ばれている。
石井
モビルスの生成AIの取り組み状況は、エンドユーザーとなるお客さまとのタッチポイントにはまだ活用できていません。現在は要約やFAQ、VOC※抽出に取り組んでいます。特にボイスオペレーションのアフターコールワーク※については、ROIの面でもインパクトの出やすいところだと考え、注力しています。これは、すでに音声認識された対話内容の要約にかかる1分から1分半ほどの時間を、削減する取り組みです。ユーザー企業からは要約が30秒ほどで出力されれば現場で使えるものになるとの声があり、30秒以内に出力することを目標に開発を行っています。現在は30秒以内の出力が達成できており、反応は良いです。
※ VOC:Voice of Customer(ボイス・オブ・カスタマー)の略。アンケートやクチコミ・問い合わせなど顧客からのあらゆる評判や感想など「顧客の声」の総称。
※ アフターコールワーク:アフターコールワーク(ACW)とは、コールセンターのオペレーターが通話終了後に行う作業のこと。具体的には、通話内容の記録、顧客情報の更新、必要なフォローアップの手配などのタスクを行う。
生成AIの活用で克服すべき最大のボトルネックは何か
―今後、生成AIがキャズムを超えるためにはどのようなボトルネックがあり、どうすれば解決できるでしょうか。
大柳氏
生成AIの課題としてよく挙げられるのが、セキュリティやハルシネーションの問題です。セキュリティについては、MicrosoftのAzureのように「基本的に二次利用しない」「処理したデータはすぐに消去する」という対策がリスク回避のためにも進んでいくと思います。ハルシネーションについても、既に回答の範囲を狭める方法などがあり、解決に向けて進んでいくと思います。

ただ、コストの問題については、どうなるのかわからないところです。例えば、現在はトークンによって課金されるといった課金形態が主流ですが、これらが受け入れられるかは分かりません。経営者としては、固定料金だとわかりやすいのですが、話せば話すほど課金されていくとなると投資判断が難しいのです。いかに送信するトークンの量を減らすかは、今後考えていくべきポイントだと思います。
また生成AIを現場で使用する側で言うと、技術の進歩によって「運用をどう変えていかなければならないのか」もまだ見えないところはあります。クラウドサービスは知らない間に仕組みが変更され、それまでのオペレーションが通用しなくなることもあります。技術がアップデートされるたびに、ハルシネーション対策も色々なことをやっていかなければならないのではないかといった懸念もあります。その辺りがクリアにならないと、先程話したキャズムは超えることができないのではないかと思います。
石井
弊社側でもコストの問題は大きいです。例えばGPT-4.0を使うと、ROIはおそらく出ません。また現場で活用するためには処理スピードが大切なのですが、何十から何百席分の通話を同時に処理していくこともあるので、その構成に耐え、なおかつスピードを出す必要があります。それと精度やコストとの兼ね合いがあるので、弊社も苦戦しています。
またセキュリティ対策として、個人情報を除去するアルゴリズムもなければなりません。そのような複合処理を行う場合、キャパシティの問題も出てくるため、そのパワーをきちんと確保できるのかという問題もあります。生成AIのスケールには間違いなく限界はあり、コストが際限なく上昇する可能性もあれば、途中で処理が止まってしまう可能性、リソースが割り当てられない可能性もあります。そう考えると、商用環境で使うにはまだハードルがあると感じます。今は様々なモジュールがオープンソースで出てきているので、追加学習が必要だとしてもコンパクトな形で処理できるようになると、選択肢は広がるのではないかと考えています。
また、ユーザー企業のAIに対する精度の考え方も見直していく必要があると思います。ユーザー企業はどうしても完璧を求めるのです。完璧を求めるのであれば、最上級のGPTを使用し、処理も2回行って修正をすれば、完璧な形に近付きます。しかし、それはROIの観点からすると間違いなく必要のないことです。ある程度の精度が出るのであれば、AIだけで完璧を求めて精度を高めるよりも、そこから人間が介入した方がコストを抑えることができます。しかし、このROIのバランスの取り方が理解できず、つまずく企業もあります。
大柳氏
その通りだと思います。音声認識でも多くの人が100%を求めます。ただ100%も80%も、業務効率やROIの結果が大きく変わるわけではありません。実際に人間の耳も、他人の話は80%程度しか聞こえてないそうです。20%は聞き落としているけれども、想像で補い、理解はできているのです。
しかし、音声認識でテキストになると間違いを見つけやすく、どうしても指摘してしまうのですね。これは日本人の気質だと感じています。私は音声認識の認識率ではなく、いかに業務が効率化されたのか、改善されるのかに目を向けるようにお話しするのですが、難しいところです。
生成AIによってどれくらい自動化は可能?残された有人対応で必要なこと
―コンタクトセンターは最終的にどの程度が自動化されるとお考えでしょうか。
大柳氏
最終的な目線をどこに置くかにもよりますが、基本的に、誰が対応しても同じ答えになるものは機械でも対応できるようになると思います。それが全体の半分程度ではないかと考えています。残りの半分は個人属性に関連しており、答えがそれぞれで違うなど、ある程度クリエイティブな要素が必要とされるもので、機械で対応ができないのではないかと考えています。

石井
私は8割を自動化できるのではないかと考えています。いわゆる「生成AI的な回答で対応できるもの」「個人の契約状況などに依存するもののシナリオボットで対応できるもの」で、合わせて8割になるのではないかと。現在、コンタクトセンターのBPO市場は約1兆円程度と言われていますが、そのうちの8割は生成AIを活用したものに中身は置き換わりつつも、市場規模を維持していくのではないかと考えています。
その場合は残りの2割、つまり人間が対応する部分の難易度は非常に高くなるはずです。ですので、ここに使われるソリューションも高度なものでなければならなくなります。
また、AIを利用するのであれば、通信料などの若干の違いはあるかもしれませんが、チャネルは電話でもメールでも、コストの差はなくなると思います。そうなると、お客さまの求める状況や好みでチャネルを選べば良いので、ノンボイスシフトの重要度は下がり、ボイスが残る割合は大きくなるのではないかと考えています。
大柳氏
いずれにしても声がなくなるわけではなく、声の存在するところでは高度な要求もあると思います。ボイスボットを使った自動化の話もありますが、有人対応の部分では更なる付加価値を色々と考えていかなければなりません。そうなると、音声認識に加える形での機能やサービスの拡充性がなければならないので、やはり我々としては音声認識ばかりにこだわっている訳にもいかないと考えています。
石井
もう一歩先にある、追加の処理の部分ですね。
大柳氏
そうです。音声認識そのものの価値は下がっていくと予想されますので、音声認識エンジンのみの提供ではなく、それを活かす高度なサービスを提供できるかというところまで考えていく必要があると思います。それは弊社の課題と言いますか、今後進むべき方向なのではないかと感じています。
―ノンボイスで生成AIと連携することに関して、今後の構想を教えてください。
石井
有人チャットでの、対話要約生成や回答生成を考えています。箇条書きさえあれば文章を生成することは比較的容易で、ハルシネーションも起きにくいと思います。有人チャットであれば、AIがそのままお客さまに回答するわけではなく、オペレーターのチェックも入るので安心です。
またサジェスト機能として、回答内容をドキュメントの中から作成することも予定しています。他社でも同じような機能を考えているところはあると思いますが、こうした機能をいかにスピーディーに出せるかが鍵になると考えています。それから、まだ実装までには超えるべきステップがありますが、オペレーターの応対評価の機能も取り組みたいものの1つです。実現するためには、生成AIとその他のAIを組み合わせる必要があると考えています。
大柳氏
コンタクトセンターにおいて、音声認識からの分析については昔から言われていました。特にメーカー企業などで商品開発や改善のためにVOCを活用したいという要望があります。音声認識でテキスト化し、自然言語処理による分析ツールを使うと、どういう回答が多いのかを出すことができます。
ただ、それはオペレーターも日頃から聞いていることなので認知しており、新商材のヒントにはなりません。ヒントになるのは、1日に1、2件あるかどうかといった潜在的な声です。現状の分析ツールの多くは「探しやすくするもの」であって「探してくれるもの」ではありません。そのような既存分析ツールからは抽出されにくいニーズを生成Aによって上手く捉えられるようになると、非常に画期的だと思います。
―生成AIによる自動化が進んでいった場合、人間による対応は有償化するという動きも出てくるのでしょうか。
石井
現在は、「AIが間違えておかしな回答をするのは企業の責任」とする風潮があると思います。そこで、お金を払えば、待ち時間なく人が正確な対応をするという案内をするとします。「お金を払う事がためらわれるのであればAI対応になりますが、AIは間違えることもあります。それでも無料なので許容してください」と。そのような概念が受け入れられると、企業としては非常に使いやすくなると思います。
大柳氏
その可能性はあり得ると思います。現在でも、対価を支払うことでそれなりのサービスを受けることができます。人が行うことにはそれなりの対価が発生するべきですし、一方で「機械の行うことは正しくない可能性もあります」といった対応を分けることは考えられると思います。
生成AI活用の鍵
―生成AIをはじめとしたAIを活用するために、ユーザー企業にどのようなことを伝えたいですか。

大柳氏
我々はサービスを導入して終わりではありません。結局はそれを使い続けて結果を出してもらう、業務で上手く使ってもらわないと意味がないわけです。システムを導入すれば全てが良くなると考える人がいますが、正しくはシステムを導入して、そこにある程度オペレーションを寄せていくということが必要で、それを理解して一生懸命に取り組む企業でなければ、DXの実現は難しいと思います。我々のサービスを上手く利用されているクライアント企業様には、熱意のある担当者がいます。一生懸命推進し、会社全体で使う文化を作り上げてくれる担当者がいると、最大限の効果を発揮できます。生成AIについても、そういった熱意を持った方々のパワーが必要だろうと思います。
石井
生成AIは手軽な面があるので、特に大企業は特別環境を作って皆さんに触らせようとします。「まず使ってみる」ということは良いと思うのですが、使うことが優先になっていて「実際に使うと想像していたほどではなかった」という幻滅感が出てきてしまいます。これは生成AIのポテンシャルを見誤った使い方だと思います。おそらく、幻滅する人は単に質問文を汎用型GPTに入力して良い回答が出るかどうかと試しているだけで、それでは使いものになりません。
現場で生成AIが使える形になるためには、どれだけナレッジを管理できるかにかかっています。例えば、生成AIにサジェストをさせる使い方を想定しても、色々なフォルダに入れているバラバラのドキュメントから回答を生成することはできません。それは人間でも難しいことで「AIならそのような夢のようなことが実現できるか?」と言うと、当然できないのです。一箇所に時系列で並べられていて、変更があれば変更履歴が入っている、そのようなナレッジ管理が適切にできていなければ使い物になりません。適切なナレッジ管理は、超えるべきハードルとしては高いのだろうと思います。
従来のAIでは教師データをAIに合わせる必要がありましたが、今回の生成AIでは人間に教えるのと同じような形で学習可能です。人間に対しては、きちんとマニュアルにして教えます。それと同じ方法でトレーニングできるようになっているので、ナレッジ管理のハードルは下がっているのではないでしょうか。また、ナレッジをゼロベースで作る際に要約などにAIを活用できるので、ナレッジを整えるところから、生成AIの活用はスタートできるかもしれません。
顧客体験(CX)の変革で今後起こること
―最後に、生成AIが今後のユーザーにとっての顧客体験(CX)をどう変えていくのか、お二人の考えを教えてください。
石井
まず前提として、コンタクトセンターやサポートは企業における顧客接点という意味で、現在は非常に限定された領域の話になってしまっています。日本だと「CX=コンタクトセンター=おもてなし」といった概念が強く、トップマネジメントの関心ごとになりにくいのです。
海外では、顧客接点、いわゆるCXはトップマネジメントのイシューになっていて、大企業の役員評価がNPSに連動するなど、またCxOやCCO(チーフカスタマーオフィサー)といった役職もあります。この認識の違いは大きいと感じます。我々の目指すコンタクトセンターやサポートの改革は、一部門ではできません。上層部にも働きかけられるパワフルな人がいれば全体も動きますが、一般的にはそうはいかないので、トップダウンで行いたいのです。しかし、そのトップには刺さりません。この「企業におけるCXの重要性」はきちんと訴求していきたいテーマです。
技術的なベースは整いつつあります。例えば営業プロセスにおいてもZoomでデジタルデータが取得しやすくなり、リアル店舗よりもウェブ経営やEC経営の方でトランザクションが増えているといった意味では、顧客接点におけるデータ収集のポイントも増えています。それを処理するAIも進化しています。あとはマインドです。ここが最も難しいわけですが、日本の場合は何社か成功した事例があれば続くのではないかと思います。
大柳氏
弊社ではよくアンビエントという単語を使います。環境にひっそりとたたずむといった意味です。電話やチャットは、能動的に情報を取りに行く必要があり、それには労力がかかります。そうではなく、周囲の人に話しかけるようにつぶやくだけで回答が返ってくるようにならないかと考えています。デバイスとしては、既にAmazon EchoやGoogle Homeが出てきています。こうしたものが常に自分のそばにある状態で、スムーズに回答できるように生成AIが育つと、可能性が出てくるのではないかと思っています。
また、自分専用のエージェントの存在する世界が近付いてきているとも考えます。どこで話しかけても回答することは当然として、これは自分の思考に寄せて、回答もパーソナライズしてくれるというものです。例えば「会食があるので手土産を」と言うだけで自分や相手の嗜好に合ったレコメンドをすぐに出してもらえると、非常に便利です。そういうこともできるようになるのではないかと期待しています。
石井
LLM自体が成長して、そこで初期解決できる世界が進んでいった場合、Google検索と同じく、上手く必要な知識をLLMに取り込んでもらえば良いと思います。そうすると、企業としてはわざわざコンタクトセンターを構えて回答する必要もなくなるという考え方はあるかもしれません。企業はナレッジ管理を行い、最新の情報をLLMに上手く取り込んでおけば良いのです。それなら、企業が自分の顧客のCXを全て担う必要はないという考え方にもなるかもしれません。
AIは活用により企業のCXそのものや、個人専用のエージェントなど一般消費者のQOL(=Quality of life(クオリティ オブ ライフ))もより進化させていきそうですね。これからも様々な場面でご一緒に取り組ませて頂ければと思います。今後がますます楽しみになりました。本日は貴重な機会を頂き、ありがとうございました。